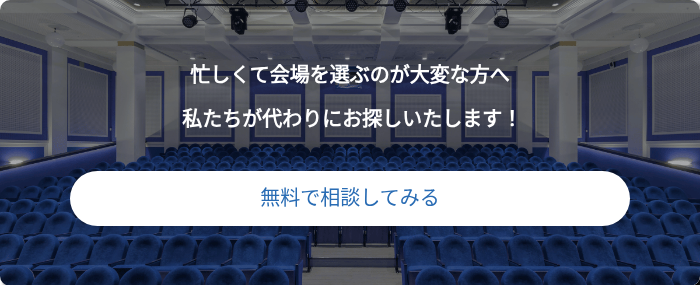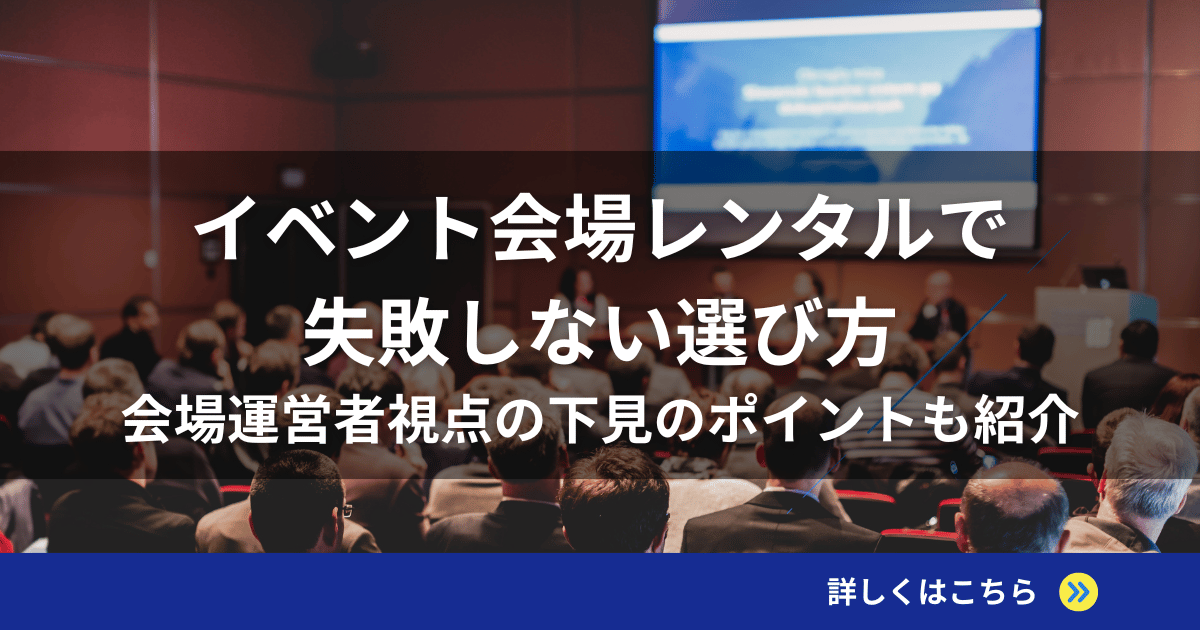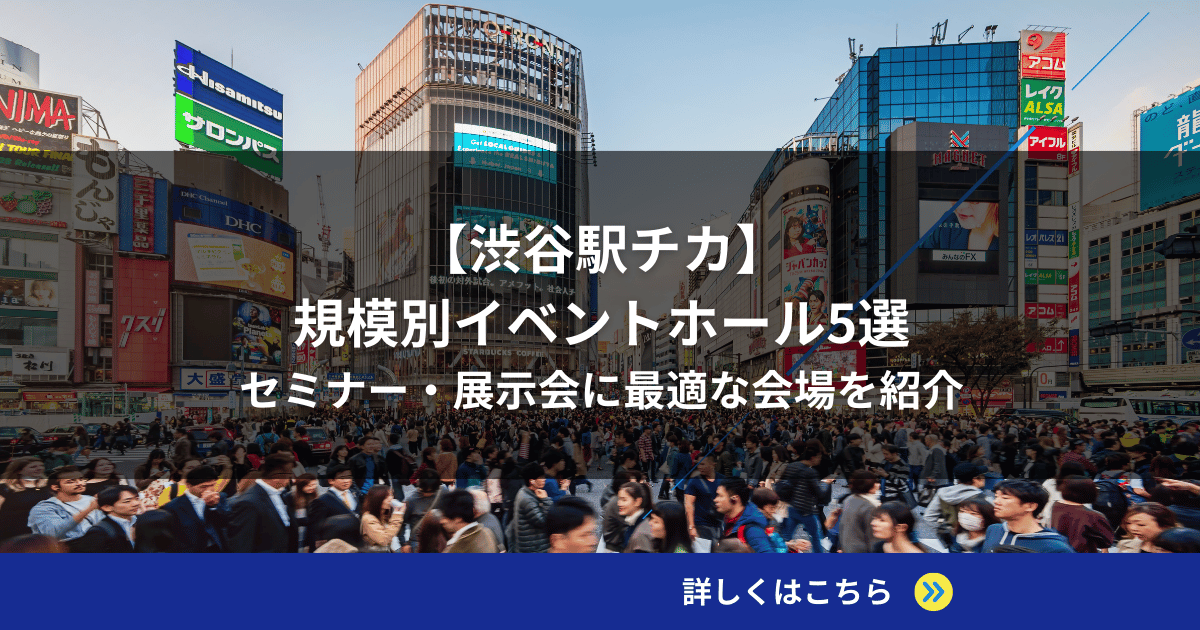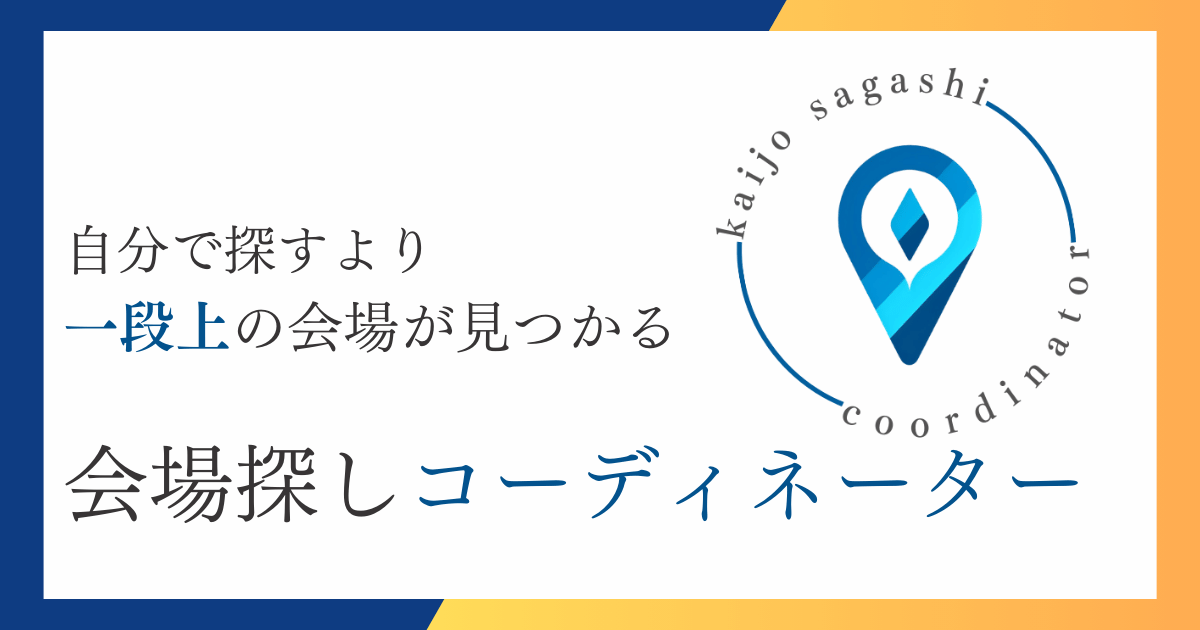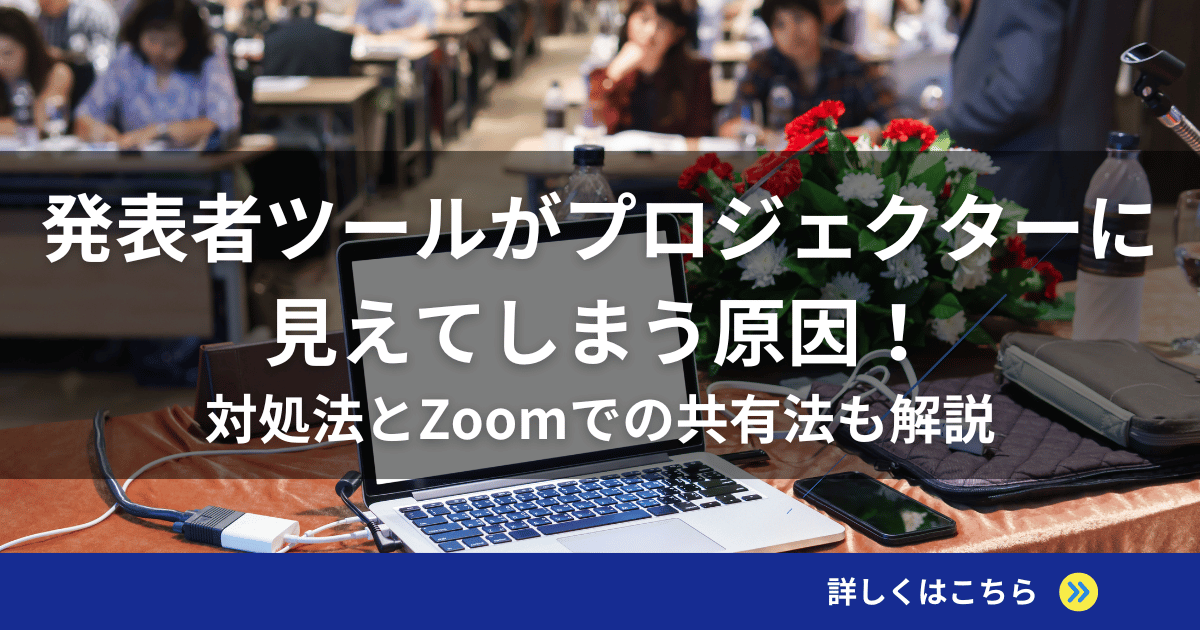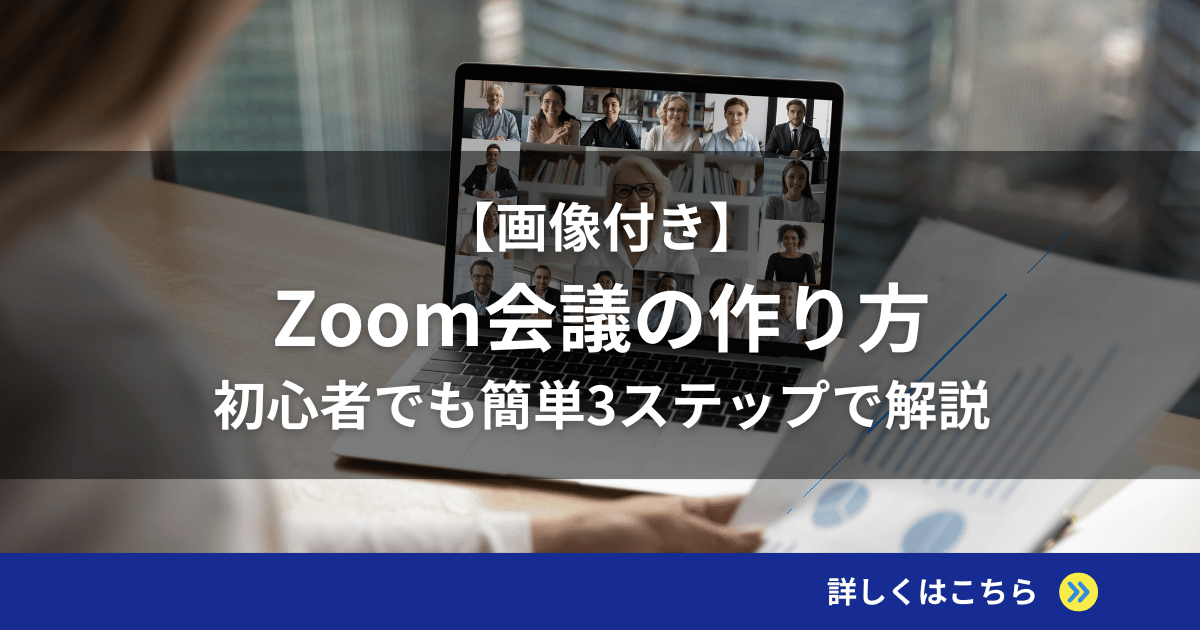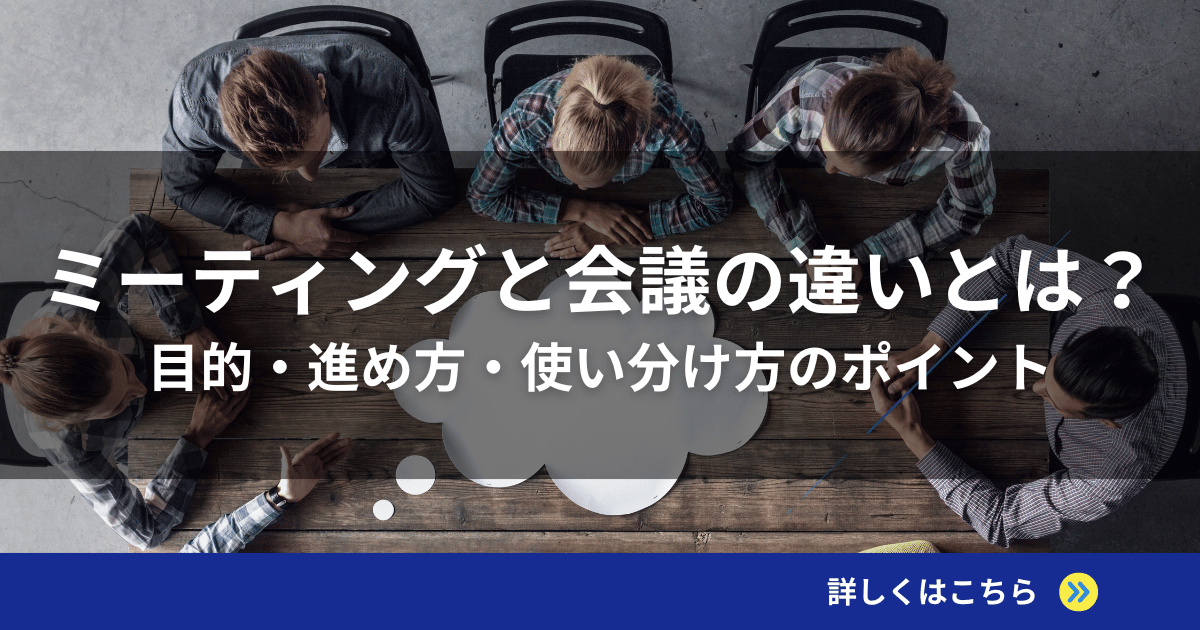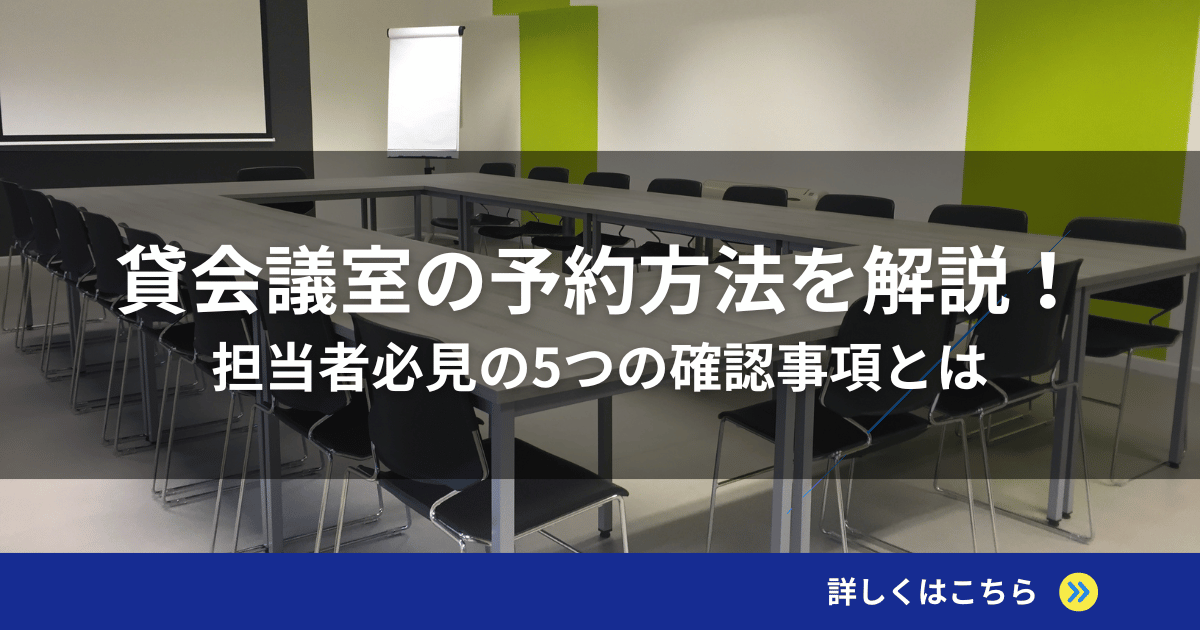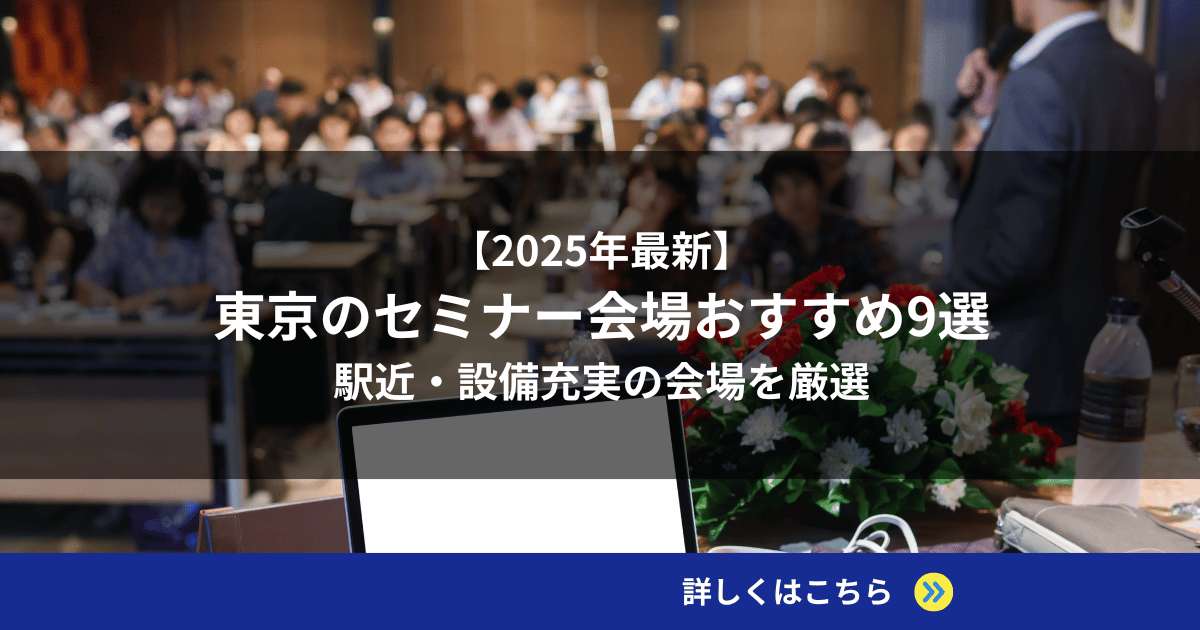会議室の上座・下座とは?レイアウト別の基本ルールも解説!
「会議室の上座って、どこなんだろう...」
「コの字型やロの字型のレイアウトだと、上座はどう変わるの?」
「お客様を案内する時、失敗したくないけど自信がない...」
このように悩む方も多いのではないでしょうか。
会議室の上座・下座は、レイアウトの形や部屋の特徴によって変化しますが、基本的な法則さえ押さえておけば、迷うことなく正しい配置決めが可能です。
この記事では、図解付きで会議室の上座・下座の基本から、様々なレイアウトでの具体的な配置方法席次まで、ビジネスパーソンとして知っておきたい席次のマナーを解説します。
ぜひ最後まで読んで、スムーズに席次を決められるようになりましょう。
目次
会議室の上座・下座とは?基本的な考え方を解説
上座(かみざ)・下座(しもざ)は、日本の伝統的なビジネスマナーにおいて重要な概念です。
特に会議室利用における上座・下座の理解は、ビジネスシーンにおける基本的なマナーとして欠かせません。
まずは、基本的な概念や原則について説明します。
上座・下座とは
上座・下座とは、席順を決める際のビジネスマナーに使われる言葉です。
上座とは、その場で最も格式が高い、あるいは地位が上の人が座るべき位置です。
一般的に、上座は「最も遠い」「最も奥」「最も安全」という3つの原則で決まります。
かつての武家社会で、最も危険の少ない場所を客人や上位者に提供していた習慣に由来します。
一方、下座は上座の対極に位置する席で、通常は出入口に近い位置に座るのが原則です。
接待する側や地位が下の者が、すぐに動けるようにという配慮から来ています。
会議室での上座・下座の原則
会議室では、出入り口から最も遠い席が上座、最も近い席が下座となります。
議長席がある場合は、出入り口から最も遠い真正面の位置に設置され、議長席の右隣が上座となり、以降は役職や社歴、年齢が高い順に左右交互に座ります。
来客がある場合は来客側が上座とするため、出入り口から遠い側、自社側は出入り口に近い側、それぞれ最上位の人が中央に座るのが原則です。
ただし、以下のような場合は原則が変更される場合があります。
- スクリーンやホワイトボードがある場合:見やすい位置を上座とする
- 窓から景観が楽しめる場合:景色が見える席が上座とする
- 出入り口が2ヶ所ある場合:より落ち着ける場所を上座とする
原則に基づきつつ、柔軟な配慮も必要です。
正しい席次が重要な理由
席次を正しく理解していると、相手への敬意を示し、信頼関係を築くのに役立ちます。
特に日本の企業文化として、上下関係を基本とした組織作りで発展してきた背景があるため、秩序を表現するうえでも重要視されています。
適切な席次を心得ていることは、ビジネスマナーへの理解と相手を重んじる姿勢の表れとして受け止められるのです。
また、参加者の立場や役割に応じた適切な席次は、会議の進行や意思決定をよりスムーズににする役割もあります。
正しい席次のマナーを身に着けていると、ビジネスパーソンとしての基本的な素養として評価され、信頼関係の構築に直結する場合もあるので、留意してきましょう。
【図解】レイアウト別の上座・下座の配置ルール
会議室のレイアウトは目的や参加人数によって様々ですが、代表的なレイアウトごとの上座・下座の配置について解説していきます。
基本的には出入り口から一番遠い席が上座となり、以降入口から遠い順に並んでいくのが原則です。
ただし、出入り口が中央になるなど、判断に困る場合は左上位という考え方に基づき、上座の左側が次の上位席の扱いになる点を覚えておきましょう。

コの字型レイアウトでの席次
コの字型レイアウトは、プレゼンテーションや研修など、進行役と参加者の関係が明確な会議で多く使われます。
コの字型のレイアウトにおける上座は、通常はコの字の中央奥の席になります。
部屋の出入口から最も離れた位置であり、且つ全体を見渡せる場所だからです。
ただし、スクリーンやプロジェクターを使用する場合は、その視認性も考慮する必要があります。
後述しますが、スクリーンとの位置関係によって、上座の位置を柔軟に変える必要性も考慮しておきましょう。
ロの字型レイアウトでの席次
ロの字型(円卓型)レイアウトは、参加者同士の対話や議論を重視する会議で使われます。
ロの字側のレイアウトでも、出入口から最も遠い位置が上座となります。
進行役がいる場合は、進行役が出入り口から一番遠い席に座り、進行役から見て左側が上座、右側が次席、以降左右交互に上位者が座っていく流れです。
スクールやシアター形式での席次
スクールやシアター形式は、セミナーや講演会など、多人数での情報共有に適したレイアウトです。
スクールやシアター形式の場合は、通常前方中央が上座となり、左隣が次席、右隣りがその次、以降左右交互で席次が決まり、後ろの列も同様の並びとなります。
ただし、進行役がいる場合は、入口から一番遠い前方かつ進行役の近くが上座となります。
円卓の場合の席次
円卓の場合は、ロの字と同じような考え方になります。
入口から一番遠い席が上座、その左隣が次席、右側がその次、以降左右交互に配置していきます。
なお、入口が中央にある場合は、左上位の考え方で問題ないですが、扉が右側にある場合、次席は上座の右側になります。
スクリーンや窓側がある会議室での上座の決め方
現代のビジネス環境では、プロジェクターやモニターを使用する会議が一般的です。
従来の上座・下座の考え方に加えて、これらの設備との関係も考慮する必要があります。
順番に見ていきましょう。
スクリーンがある会議室
現代のビジネスシーンでは、スクリーンを使用したプレゼンテーションが一般的です。
プレゼンテーション時の上座は、従来の原則よりも、スクリーンが最も見やすい位置が上座として優先されます。
プレゼンターがいる場合は、スクリーンとプレゼンターの様子が見やすい位置にするとよいでしょう。
特に重要な商談や役員会議の場合は、事前にスクリーンとの位置関係を確認し、必要に応じて座席配置を調整することをおすすめします。
必要に応じて座席のレイアウトを調整し、全員がストレスなく参加できる環境を整えるのが、会議の成果を最大限に高めるコツです。
窓側の席の扱い方
窓側の席は、基本原則に則り一般的に上座として扱われます。
ただし、窓からの眺めが良い場合は、景色の見やすい席を上座とするケースがあります。
特に重要な会議や接客を兼ねた会議では、景色の良い席を上座とすることで、リラックスした雰囲気作りが可能です。
通常のルールから外れた対応となる場合は、景色の良さなどを理由に別席をご案内する旨伝えると、失礼にとられず、相手に配慮している印象を与えられるでしょう。
プロジェクターやモニターがある場合の注意点
プロジェクターやモニターを使用する際は、機材の配置にも配慮が必要です。
まず、プロジェクターの投影光が上座に座る方の目に入らないよう注意します。
また、天吊りのプロジェクターの場合、落下の危険を避けるため、直下に席を配置しないようにしましょう。
複数のモニターが設置されている場合は、すべてのモニターが見やすい位置を上座として選定します。
加えて窓もある場合は、景色の見やすさに加え、外光の影響でモニターが見づらくならないような配慮も必要です。
どうしても視認性の良い位置を確保できない場合は、資料の印刷物を用意するなどの代替手段を検討するのもおすすめです。
来客時や入口が複数ある場合の上座選びのポイント
会議室での上座・下座の決定で特に重要なのが、来客対応と入口の位置関係です。
取引先など重要な来客がある場合は、より丁寧な配慮が必要となります。
また、複数の入口がある会議室では、どの入口を基準にするかによって上座の位置が変わってくるため、事前の確認と判断が重要です。
ここでは、来客対応時の基本的な考え方と、複数入口がある場合の判断基準、そして状況に応じた柔軟な対応方法について詳しく解説します。
来客応対での基本的な考え方
来客をお迎えする際の座席配置は、基本的には、来客に上座を提供します。
複数の来客がある場合は、来客側の序列に従って上座から配置します。
来客企業の社長が参加する場合は、その方を上座とし、両脇に来客企業の他の方々を配置するのが一般的です。
また、主催側の対応者は、来客の対面に着席するのが基本です。
これは、アイコンタクトを取りやすく、スムーズなコミュニケーションを実現するためです。
入口が複数ある会議室での判断基準
複数の入口がある会議室では、以下の基準で主たる入口を決定し、それを基準に上座を設定します。
- 普段最も使用頻度が高い入口
- 来客が案内される可能性が高い入口
- エレベーターやエントランスから近い入口
ただし、当日の状況に応じて、実際に来客が入室する入口を基準とする場合もあります。
他にも、高齢の方や体調がすぐれない方がいる場合は、出入りのしやすさを考慮して、通常の上座・下座の位置を変更するなどの配慮も必要です。
例外的な対応は発生しうるものとして、通常と異なる案内をする場合は、その理由を丁寧に説明し、関係者の理解を得られるように努めましょう。
【番外編】知っておくと便利なビジネスシーンでの席次マナー
会議室での上座・下座の理解に加えて、ビジネスパーソンとして知っておくと重宝する席次のマナーがあります。
社外での移動や会食など、様々なビジネスシーンで活用できる席次のルールについて解説していきましょう。
特に取引先との外出や接待の際に役立ちますので、チェックしてみてください。
タクシー・ハイヤーでの席次
ビジネスでの移動時、特にタクシーやハイヤーでの席次も重要なマナーの一つです。
タクシーでの上座は、以下の通りです。
| タクシー・ハイヤーの基本的な席次(4人で乗る場合) |
|---|
上座から下座の順番
|
人数によって2人なら1.4、3人なら1.2.4の順で座ります。
通常、目下の人が助手席に座り、道案内や支払いなども担当します。
なお、女性が同乗する場合、後部座席の中央を避けたり、ヒールを履いている際は乗り降りなどのしやすさにも配慮が必要でしょう。
電車・新幹線での座席選び
電車や新幹線では、座席の配置によって上座・下座の考え方が異なります。
二人掛けの場合は、窓側が上座・通路側が下座です。
三人掛けの場合は、窓側が上座・通路側が次席・中央が下座になります。
ボックス席の場合は進行方向を向いた窓側が最上座、進行方向の反対の通路側が下座です。
ただし、あくまで原則となるため、特に長時間の移動では上位者の希望を確認し、通路側を好む場合は柔軟に対応しましょう。
接待や会食時の席次マナー
飲食店での接待や会食時の席次も、ビジネスマナーとして押さえておくべき重要なポイントです。
和室の場合、床の間に最も近い席が上座となります。
床の間がない場合は、入口から最も遠い位置、または座敷の奥まった位置が上座となります。
テーブル席の場合、入口から最も遠い位置、または窓側の位置が上座となります。
来客が複数の場合は、上座を起点に、地位や年齢などに応じて席次を決めていきます。
特に注意したいのは、主催者側の立場です。
接待する側の最上位者は、来客の上座に対面する位置に着席し、適切なタイミングでの対応ができるようにします。
まとめ:会議室の上座・下座の前提を押さえ、柔軟に席次を決めましょう
会議室での上座・下座の配置は、一見複雑に思えるかもしれませんが、基本的な原則を押さえておけばどのレイアウトでも迷うことなく判断できます。
ここまでの内容を踏まえて、重要なポイントを整理しましょう。
まずは、「最も遠い」「最も奥」「最も安全」という3つの基本原則を常に意識することが大切です。
出入口から最も遠い位置を基準に考え、窓側とスクリーンの位置、さらには来客の有無などの要素を総合的に判断していきます。
ただし、会議の目的や参加者の状況に応じて、臨機応変な対応も必要です。
レイアウト選びに迷った際は、会議室を提供している会場スタッフに相談するのがおすすめです。
基本のレイアウトだけでなく、席次を意識した座席配置など、柔軟にレイアウトの相談に応じてくれるだけでなく、過去の実績や経験に基づいて、適切なレイアウトを提案してくれます。
会議室など、外部の会場をお探しの際は「会場探しコーディネーター」へご相談ください。
Author Profile
会場探しコーディネーターメディア編集部
運営会社:株式会社シアターワークショップ
“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。
最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。
本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。
▼お問い合わせフォーム▼
会場探しのご相談はコチラ
Pick Up
関連記事
「ミーティング」と「会議」——この2つの言葉の使い分けに迷った経験はありませんか? 同じように思える言葉でも、その目的や特徴には大きな違いがあるのです。
「初めて外部の貸会議室の予約を任されたけど、何を確認すればいいのかわからない…」 「予約の具体的な手順を知りたい」 「キャンセル料っていつからかかるの?」 会議室の予約の際に、このように考える方も多い...