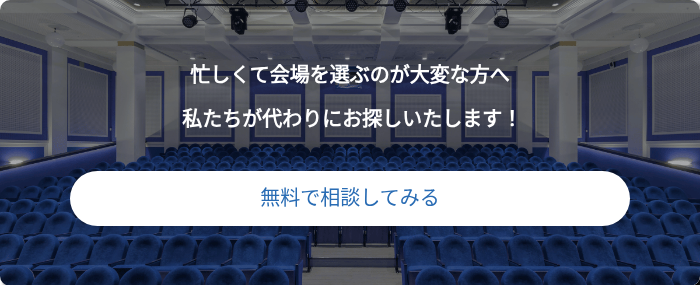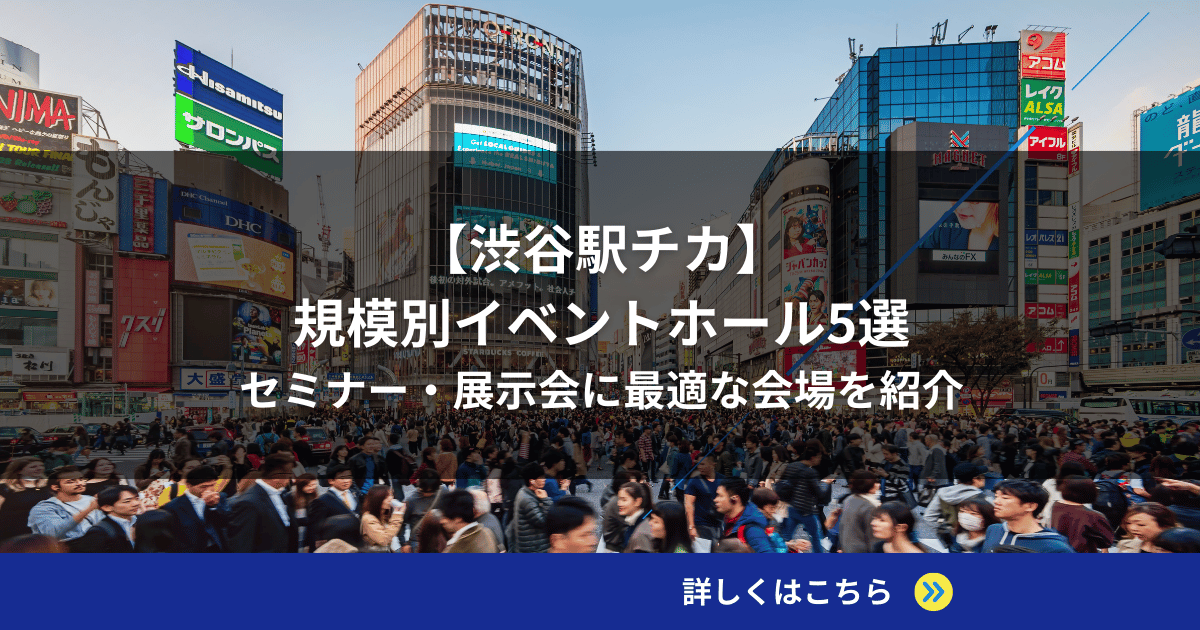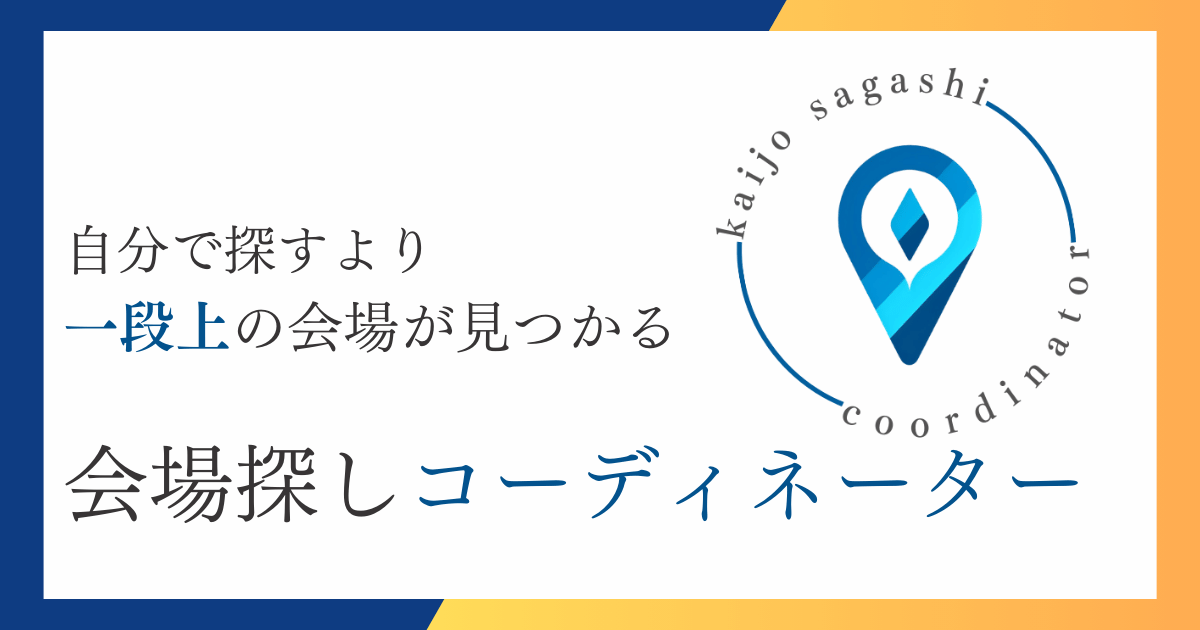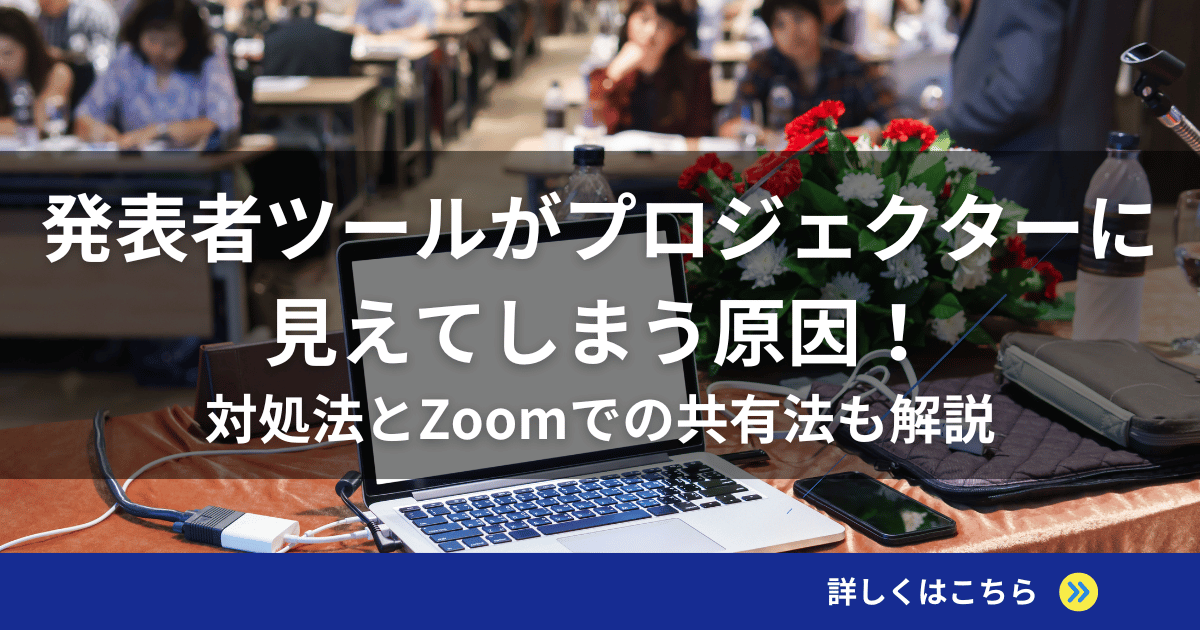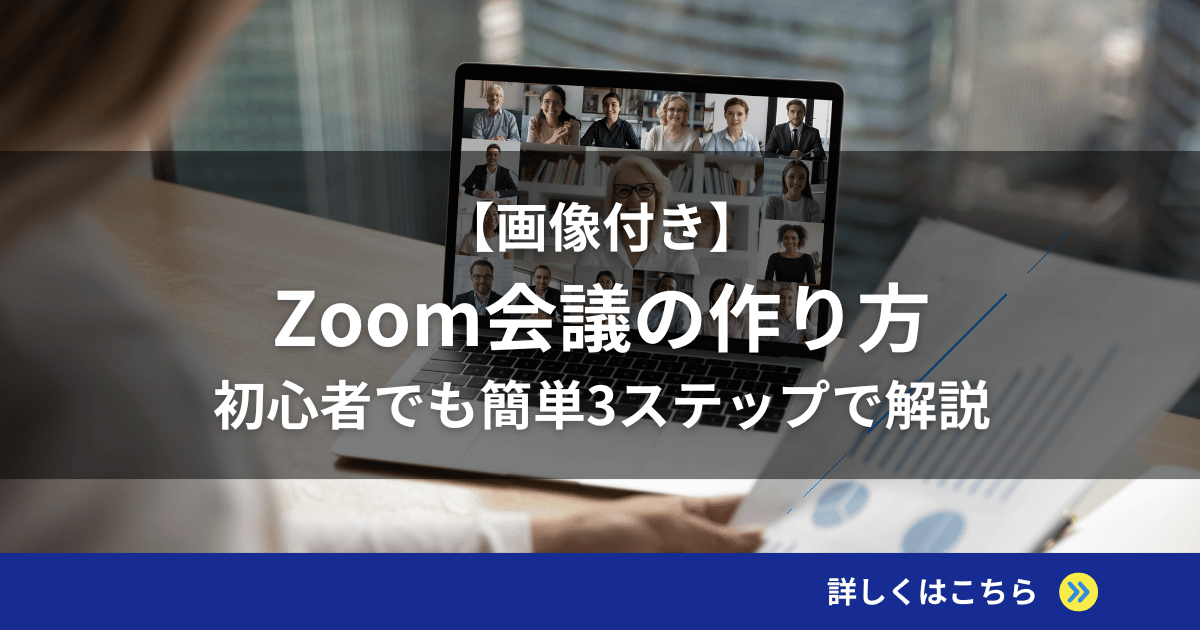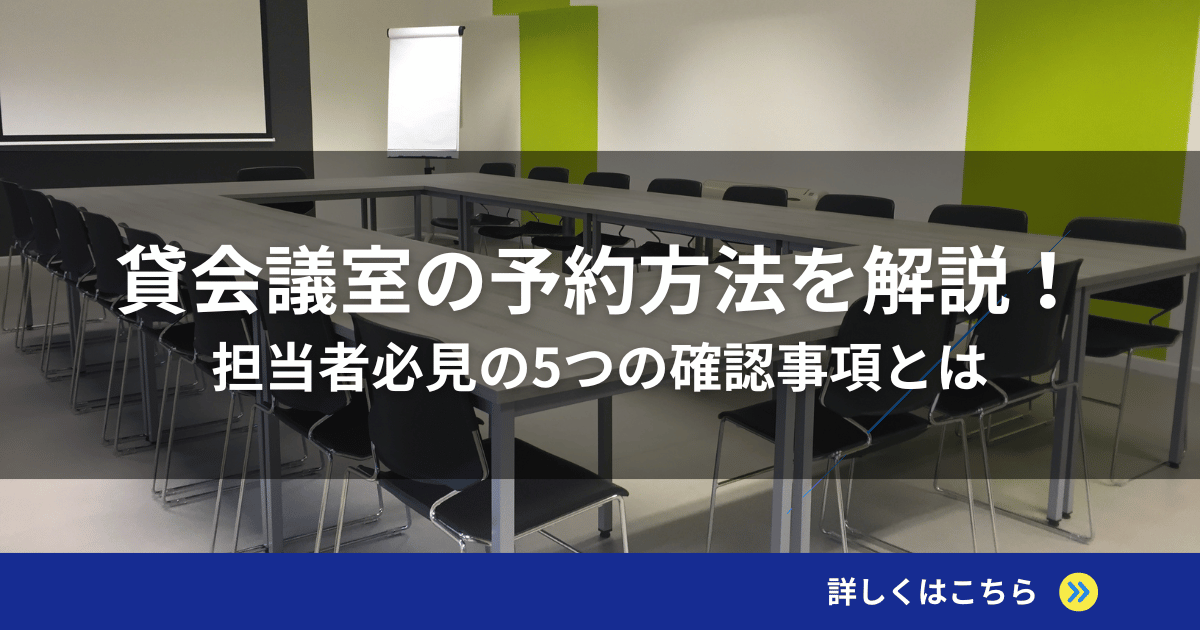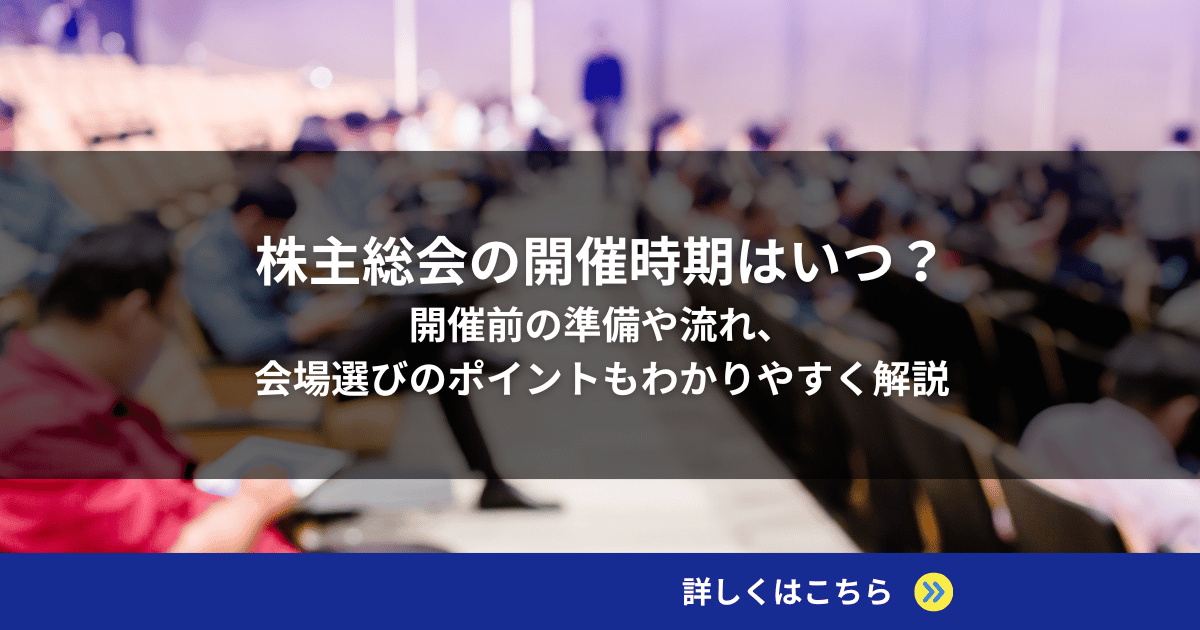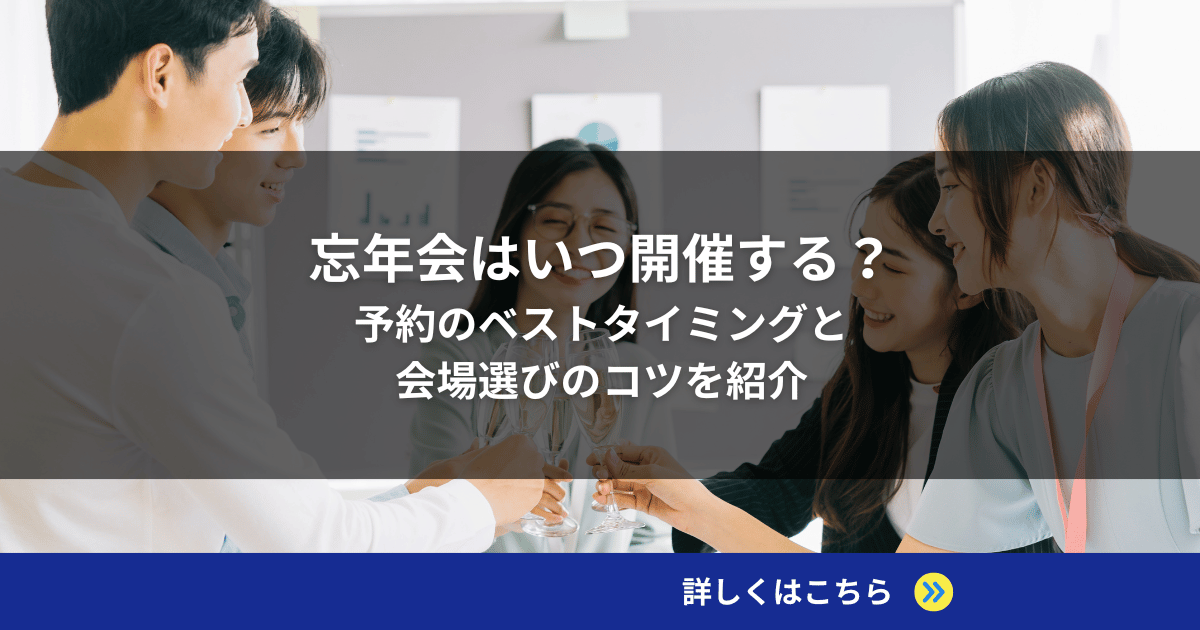ハイブリッド開催のメリットデメリットとは?失敗しない会場選びの方法も解説
コロナ禍以降、生活様式の変容とともに、イベント開催形式の大きな変化を実感した人も多いのではないでしょうか。
オンライン開催が一般化する一方で、リアルでの場、対面でのコミュニケーションの価値も再認識されています。
そんな中で注目を集めているのが「ハイブリッド開催」です。
しかし、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド形式は、機材の準備や運営方法など、初めて担当する方にとっては不安が多いものです。
「どんな準備が必要?」
「予算はどれくらい?」
「当日の進行は大丈夫?」
といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。
本記事では、ハイブリッド開催の基礎知識から具体的な実施方法、成功のポイントまで、初めての担当者でも安心して取り組めるよう、わかりやすく解説します。
ハイブリッド形式に合った会場選びのコツや、プロに相談する方法についても詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
→ ハイブリッド形式のイベントにも対応した渋谷駅チカのイベントホール5選はコチラ
目次
ハイブリッド開催とは?その定義と基本的な特徴

近年、ビジネスシーンで頻繁に耳にするようになった「ハイブリッド開催」。
ハイブリッド開催とは、会場での対面参加とオンラインでの遠隔参加を組み合わせたイベント形式のことです。
ハイブリッド開催のイベントは、近年全世界を巻き込んで発生したパンデミックを機に、働き方改革の推進や、効率的なコミュニケーション方法への需要の高まりがきっかけで注目されるようになりました。
ハイブリッド形式での開催によって、参加者は自身の状況や希望に応じて、会場での参加かオンラインでの参加かを選択可能です。
また、オンラインと併用するからこそ、演出の幅は非常に広がっています。
ハイブリッド開催のメリット

ハイブリッド開催のイベントのメリットは、以下の通りです。
| ハイブリッド開催のメリット |
|
それぞれ解説します。
メリット1.地域や国を超えた参加が可能に
従来の対面イベントでは、遠方からの参加者に交通費や時間的コストが発生していました。
また、キャパシティの問題で参加人数にも限りがあったのも事実です。
しかし、ハイブリッド開催では、オンライン参加というオプションにより、地理的な制約を超えた参加が可能になります。
具体的には、以下のような場面で特に効果を発揮します。
| ハイブリッド開催が効果を発揮する場面 |
|
これにより、より多くの方にイベントの価値を届けることができます。
メリット2.アーカイブの活用でイベントの価値が持続
オンライン配信を行うことで、イベントの録画データを残しやすくなりました。
ZOOMやTeamsなどのオンライン会議ツールは、いずれも録画機能を標準装備しており、簡単に記録が可能になっています。
例えば記録したアーカイブ映像は、当日参加できなかった方への後日共有や、社内の教育資料として活用できます。
一度きりのイベントだったものを、継続的に価値を生み出すコンテンツへと変えることができるのです。
メリット3.双方向コミュニケーションの促進
ハイブリッド開催により、デジタルツールを活用した参加者との対話のハードルが下がったため、双方向のコミュニケーションを生み出しやすくなっています。
チャット機能やリアルタイムアンケートなどのオンラインツールを使用すれば、従来の対面イベントでは実現が難しかった、より活発で多様なコミュニケーションが可能となりました。
例えば、大勢の前で手を挙げて質問することに抵抗がある方でも、チャットを通じれば積極的に質問や意見を投稿できます。
また、発表者や登壇者にとっても、参加者からのリアルタイムな反応や質問を随時確認しながら進行できるため、より柔軟で参加者のニーズに応じたプレゼンテーションが可能になります。
オンラインを取り入れることで、一方通行の情報提供ではなく、参加者との活発な対話を実現する真の双方向コミュニケーションが実現できるようになったと言えます。
ハイブリッドイベント開催の実績がある渋谷駅チカの多目的ホールを使えば、よりメリットを生かしたイベントを開催可能です。
ハイブリッド開催のデメリット

ハイブリッド開催のメリットは、人数や場所の制限をなくし、コミュニケーションのあり方を変えたことでしたが、一方で取り入れるための課題が存在します。
| ハイブリッド開催のデメリット |
|
デメリット1.機材や技術的な準備が必要
ハイブリッド開催では、従来の会場設営に加えて、オンライン配信用の機材準備が必要となります。
具体的には、高画質カメラ、集音性の高いマイク、配信専用PCなどの機材確保に加え、安定したインターネット環境の整備も求められます。
もし既存で持っていない場合は機材の購入、もしくはレンタルや外部業者に委託するなども検討が必要です。
ハイブリッド形式にするための準備には、通常の対面イベント以上の時間と労力や初期コストがかかります。
デメリット2.運営の手間が増加
ハイブリッド形式でイベントを開催する場合、従来通りの会場での進行に加え、オンライン配信の両方に対応する必要があるため、運営スタッフの業務量が増加します。
会場での案内や進行管理に加えて、場合によってはオンライン参加者向けの専任のスタッフの配置も必要です。
例えば、オンラインでの登壇社がいる場合は、現地とは別で、個別での直接やり取りが生じます。
外部からの参加者が多いほど対応が煩雑になるため、より人員配置の計画も綿密にしていく必要があります。
デメリット3.一体感の構築に課題が残る
ハイブリッド形式での開催の場合、対面参加者とオンライン参加者の間で、参加体験に差が生じやすいという課題があります。
特にグループディスカッションやワークショップなど、参加者同士の交流が重要となるセッションでは、オンライン参加者が孤立感や疎外感を感じることのないよう、細やかな配慮と工夫が必要です。
例えば、オンライン参加者も気軽に発言できる環境づくりや、対面・オンライン参加者を混合したグループ編成など、双方が活発に交流できる仕組みを整えることが重要です。
一方でセミナー開催などであれば、会場参加ならではの付加価値を意図的につけることも必要になるため、あえて差をつける場面もあるでしょう。
具体的にはリアル参加者限定での懇親会開催など、会場参加の特別感や優位性の演出をはかり、参加形態による自然な差別化を作り出すことも可能です。
事前に入念な準備と計画を実施し、それぞれの参加者にとって満足度の高いイベントになるように配慮する必要があります。
ハイブリッド開催しやすいイベント事例3選

ハイブリッド形式のイベントには、相性の良いイベントが存在します。
ここでは特に相性がよく、比較的取り組みやすいイベント開催例をご紹介します。
代表的なモデルケースから、効果的な運営のポイントを見ていきましょう。
①社員研修や勉強会
全国各地に拠点がある企業にとって、ハイブリッド形式は理想的な選択肢になり得ます。
なぜなら、本社でのリアル参加者に重要な内容を直接的に伝えながらも、地方拠点の社員にもリアルタイムで同様にメッセージを届けることができるからです。
オンラインとはいえ、リアルタイムでの参加となれば、熱量なども感じやすく、一体感を演出しやすいため、全国の拠点に対して、均一な情報提供と質の高い研修を実現可能です。
また、録画データを社内の教育資料として活用することで、後日の振り返りや新人社員教育にも活用できるため、社内での研修効果を最大化できます。
②採用イベントやキャリアセミナー
採用イベントやキャリアセミナーのハイブリッド開催は、特に地方在住の就職活動中の学生とって活動しやすくなるきっかけになるでしょう。
就職活動中の学生は時間や交通費の制約が大きいため、オンライン参加があると参加のハードルが下がります。
例えば、マイナビが主催する「仕事研究&インターンシップEXPO」では、従来型のリアルブースでの合同会社説明会と、オンラインでの動画配信を組み合わせた形式で開催されました。
学生側は対面説明とオンライン視聴を、自由に選択できる形式となっています。
ハイブリッド形式によって、企業側にとっても地方の優秀な人材を集められる可能性が高まるため、学生と企業双方にとって効果的な採用活動を実現する手段となっています。
③学会やカンファレンス
海外や地方からの参加者を含む大規模なイベントでも、ハイブリッド形式が効果的です。
現地での発表や交流を重視しながら、遠方からの参加者もオンラインで研究発表や議論に参加できます。
渋谷にあるヒカリエホールで開催された「GRIC2024」では、成長産業に特化した国内最大級のカンファレンスとして、ハイブリッド形式で実施されました。
日にちや時間帯によってオンラインのみ・オフラインのみのセッションや、ハイブリッドでのセッションなど、組み合わせながら変えて実施することで、海外からのスピーカーの登壇にも柔軟に対応しています。
ハイブリッド開催の会場をお探しの方は、
「会場探しコーディネーター」へご相談ください。
ご希望条件に合わせてまとめて会場をご提案させていただきます。
ハイブリッド形式で開催する方法4ステップ

成功するハイブリッドイベントには、入念な準備と計画が不可欠です。
ここでは、イベントの企画から本番までの具体的な実施手順を、4つのステップに分けて解説します。
それぞれの段階で押さえるべきポイントを理解し、実践することで、対面とオンライン双方の参加者に満足度の高いイベントを実現できます。
1. 目的を明確にする
ハイブリッドイベントを成功に導くための最初のステップは、明確な目的設定です。
イベントの目的に応じてリアルとオンラインの参加者のバランスや、会場選定・レイアウト作りにも関わるからです。
イベントで何を達成したいのか、具体的なゴールを定めることで、最適な開催形式が見えてきます。
例えば、参加者数の最大化が目的であれば、オンラインの参加枠を広く設定し、地理的な成約なく多くの方が参加できる環境を整えることが重要でしょう。
一方で、深い議論や参加者同士の交流を重視する場合には、会場参加者の比率を多めに設定し、グループワークや交流会に適した会場レイアウトを検討する必要があります。
最適なバランスを設計することで、より効果的なハイブリッド形式のイベントを実現できるでしょう。
2. 会場と日時を決定する
ハイブリッド開催の成否を大きく左右するのが、適切な会場の選定です。
オンライン配信に対応できる会場には、いくつかの必須要件があります。
重要なポイントは、以下の通りです。
| ハイブリッド開催のデメリット |
|
高速かつ安定したインターネット環境は必須条件ですが、それだけでなく、十分な電源供給能力や質の高い音響設備も欠かせません。
また、配信機材の設置やスタッフの配置のために十分なスペースが確保できるかどうかも確認が必要です。
リアル会場の参加人数を優先する場合、どうしても配信で使用できるスペースは限られてきます。
特に、カメラの設置位置や配信用PCの配置場所など、細かなレイアウトまで考慮に入れた会場選びを心がけましょう。
日程は会場の空きはもちろん、参加者募集のタイミングや効果的な告知をするのに、適切な時期を選ぶと集客の最大化につながります。
3. 必要な機材とスタッフを準備する
ハイブリッド開催を実現するには、必要な機材を揃えて、それが扱えるスタッフの手配が必須です。
| 配信に必要な機材例 |
|
ハイブリッド開催では、従来の対面イベント以上に入念な準備が必要です。
配信用カメラは、できれば複数台用意し、様々なアングルからの撮影を可能にすることをおすすめします。
また、集音マイクも、発表者用、質疑応答用など、用途に応じて複数準備するのが望ましいでしょう。
スタッフの役割分担も重要で、会場運営担当、配信技術担当、オンライン参加者対応担当など、それぞれの役割を明確にし、必要な人数を適切に
配置することで、スムーズな運営が可能になります。
特にオンライン参加者向けの専門スタッフは、チャットでの質問対応やトラブルシューティングなど、重要な役割を担います。
リアルイベントのみと違い、対応すべきポイントも増えるため、必要に応じて配信業務の外注化も視野に入れると良いでしょう。
4. 動作チェックとリハーサルを徹底する
本番でのスムーズな進行を実現するためには、入念な事前確認とリハーサルは必須でしょう。
特に、ハイブリッドイベントでは、会場内だけでなく、オンライン参加者の視聴環境にも気を配らなければなりません。
| 本番前に必ず確認すべき項目例 |
|
本番でのトラブルを防ぐため、インターネット回線の速度と安定性、音声・映像の質、配信プラットフォームの動作確認などは特に入念にチェッ
クを行います。
また、スタッフ間の連携や役割分担の確認、そしてトラブル発生時のバックアッププランの確認まで、できる限り実際の状況を想定したリハーサ
ルを実施するのがおすすめです。
特に、オンライン参加者の視点に立ったチェックが重要になります。
実際に配信映像や音声を確認し、遠隔地からの参加者にとって満足できる品質が確保できているか、確認することが大切です。
また、質疑応答のシミュレーションなど、インタラクティブな要素についても事前に動作確認を行っておくべきでしょう。
これらの準備を入念に行うことで、本番でのトラブルを最小限に抑え、参加者全員が満足できるイベントの実現が可能になります。
ハイブリッド開催を成功させる会場選び3つの視点

ハイブリッド開催の成否を大きく左右するのが、適切な会場の選定です。
単なるリアルイベント用の会場とは異なり、オンライン配信に必要な設備や環境にも配慮が必要です。
ここでは、会場選びの際に確認すべき具体的なポイントと、見落としがちな注意点を詳しく解説します。
ポイントを押さえることで、ハイブリッド開催に最適な会場を選ぶことができます。
①必要な設備が整った会場を選ぶ
ハイブリッド開催の質を決定づける要素として、会場の設備環境が肝となります。
|
ハイブリッド開催に不可欠な設備 |
|
安定した高速インターネット回線は必須条件ですが、それだけでなく、クリアな音声を届けるための高品質な音響設備や、配信映像の質を確保す
るための適切な照明設備も重要です。
さらに、配信機材やパソコンなどの電源が必要な機材を多く利用するため、安定して供給できる設備も必要不可欠です。
設備が整っていない場合、外部から機材を持ち込む必要が生じ、準備の手間やコストが増大します。
また、設備のトラブルはイベント全体の質に直結するため、事前の入念なチェックと、信頼できる会場の選定が重要です。
②プロのオペレーターを依頼できる会場を選ぶ
ハイブリッド開催における技術面での不安を解消し、質の高いイベントを実現する重要な要素が、プロの配信オペレーターの存在です。
専門スタッフのサポートにより
|
など、ハイブリッド開催ならではの負担を軽減することが可能です。
専門のオペレーターがいる、もしくは手配できる会場を選ぶことで、主催者は内容や参加者とのコミュニケーションに集中できます。
また、トラブルが発生した際も、プロフェッショナルによる迅速な対応が期待できます。
特に初めてハイブリッド開催に挑戦する場合は、経験豊富なスタッフのサポートがあることで、運営側の不安や負担を大きく軽減可能です。
外注することでコストがかかりますが、イベントの質を確保する上で、十分な投資価値があると言えるでしょう。
③ハイブリッド開催実績のある会場を選ぶ
ハイブリッド開催の経験が豊富な会場を選ぶことで、数々の実践から得られた知見を活用できます。
ハイブリッド開催を多く受け入れてきた会場であれば、過去の成功事例をもとにした会場の利用方法や提案をうけられる可能性が高いです。
実際に合ったトラブル事例などをもとに、よりスムーズな運営ができるようなアドバイスも得られるため、トラブルを未然に回避することにもつながります。
また、カメラの配置やスクリーンの設置などのレイアウトについても、実際の事例をもとに最適な配置を教えてもらえるでしょう。
さらに、実績がある過剰はスタッフが配信機材やシステムに精通していることが多く、外部から配信業者を連れてくることになった場合でも、打ち合わせがスムーズに進行します。
当社が運営している会場でも、ハイブリッド開催の実績がある会場は複数あります。
渋谷の駅チカ物件を探している方は、【渋谷駅チカ】規模別イベントホール5選|セミナー・展示会に最適な会場を紹介の記事もご確認ください。
ハイブリッド開催のイベント成功は会場選びから始まります

ハイブリッド形式でのイベント開催には、従来の対面形式以上の準備と配慮が必要です。
しかし、適切な計画と実施により、対面とオンラインそれぞれの利点を活かした、より価値の高いイベントを実現できます。
その成功の鍵を握るのが、適切な会場の選定です。
当社の会場探しコーディネーターでは、お客様のイベントの目的や規模に応じて、ハイブリッド開催に最適な会場をご提案いたします。
必要な配信機材の手配から、経験豊富なスタッフによる当日の運営サポートまで、ワンストップでご提供することも可能です。
はじめてのハイブリッド開催に不安をお持ちの方も、豊富な実績を持つ当社コーディネーターが、企画段階から成功に向けた具体的なプランをご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
Pick Up
関連記事
「初めて外部の貸会議室の予約を任されたけど、何を確認すればいいのかわからない…」 「予約の具体的な手順を知りたい」 「キャンセル料っていつからかかるの?」 会議室の予約の際に、このように考える方も多い...
「忘年会っていつ開催するのが一般的なんだろう?」 「会場予約はいつから始めれば良いの?」 そう悩んでいる幹事の方も多いのではないでしょうか。