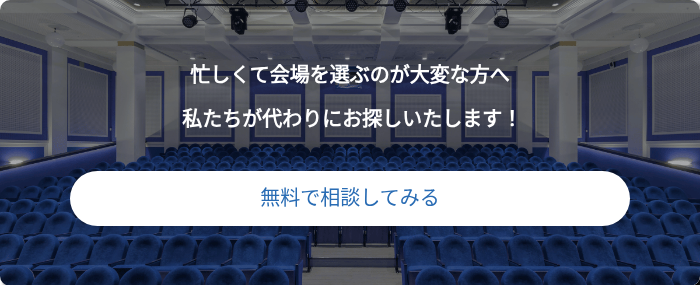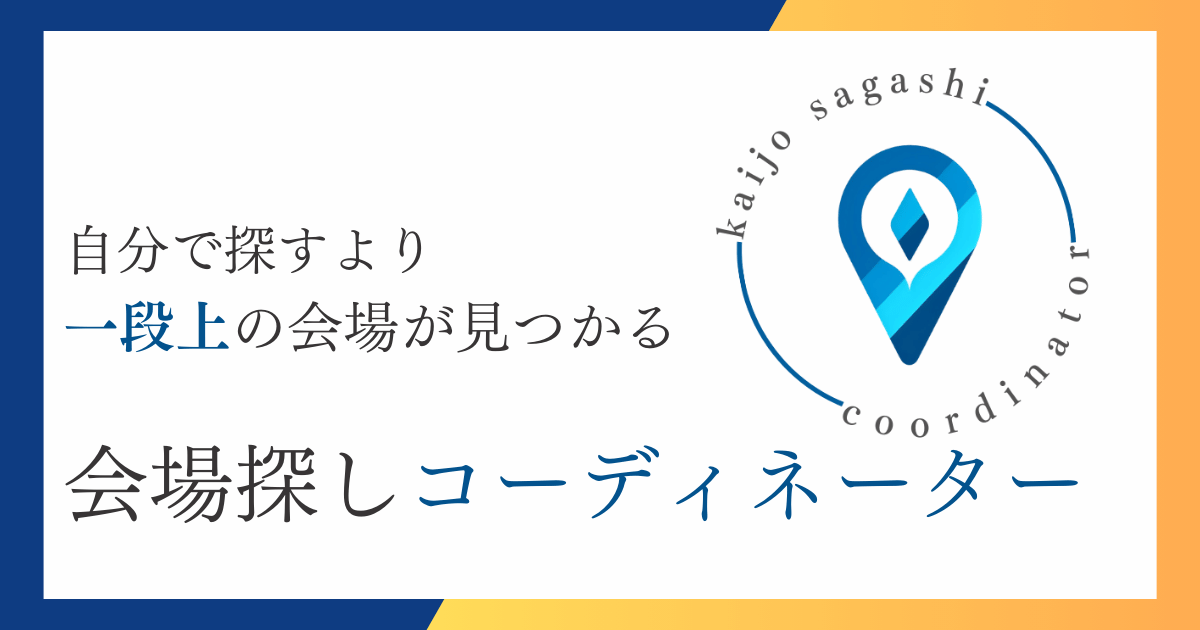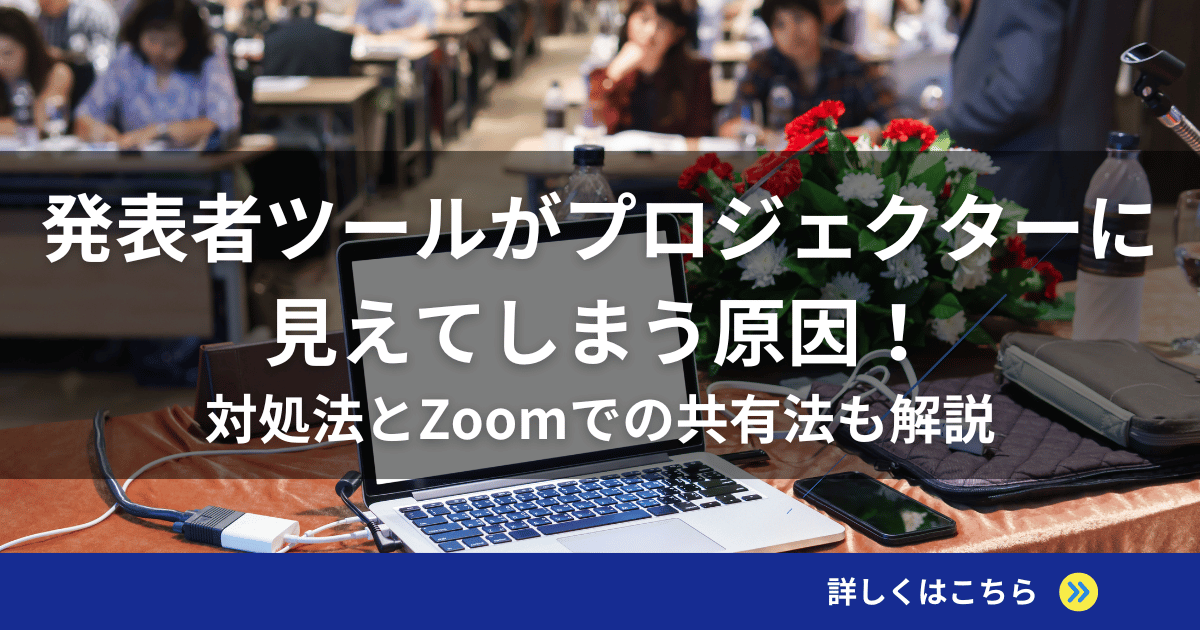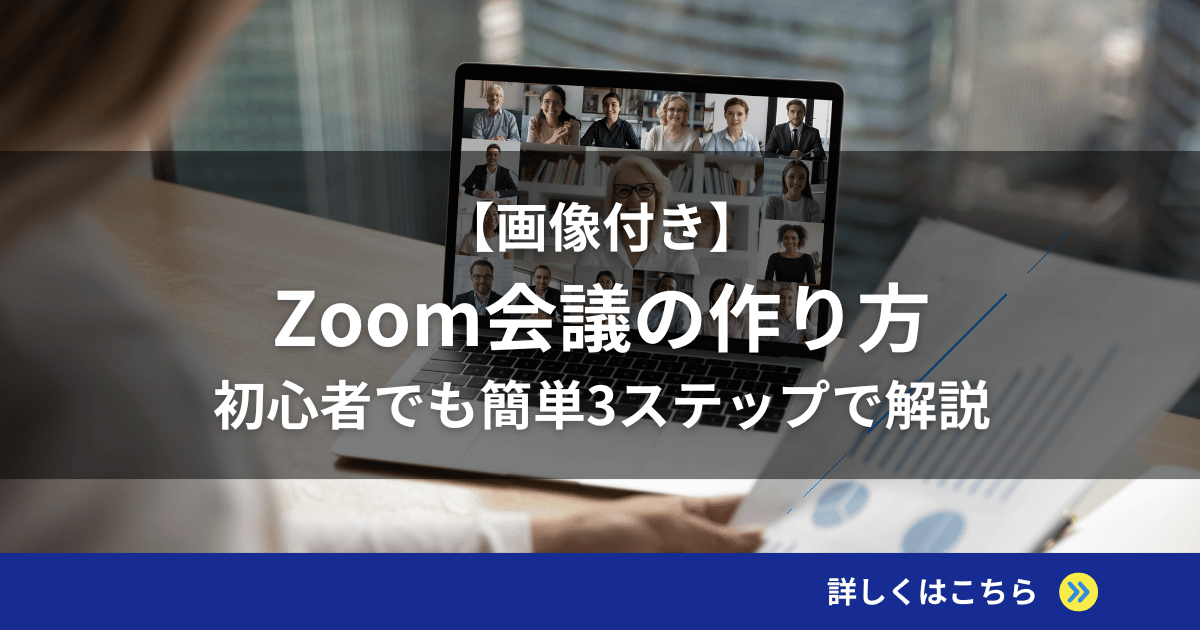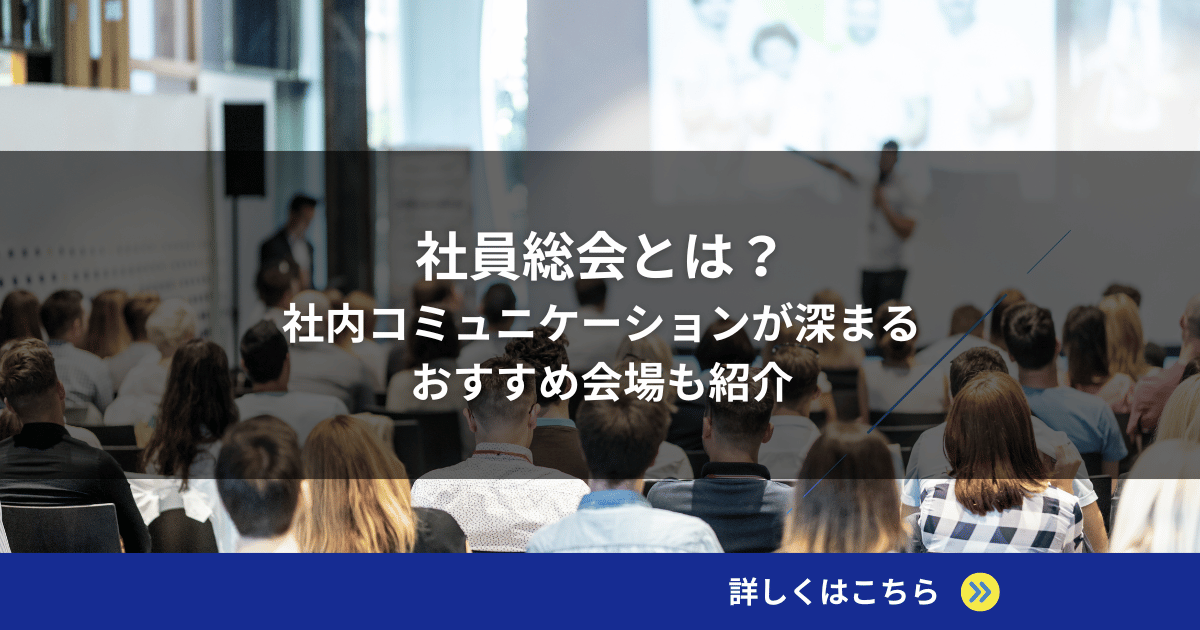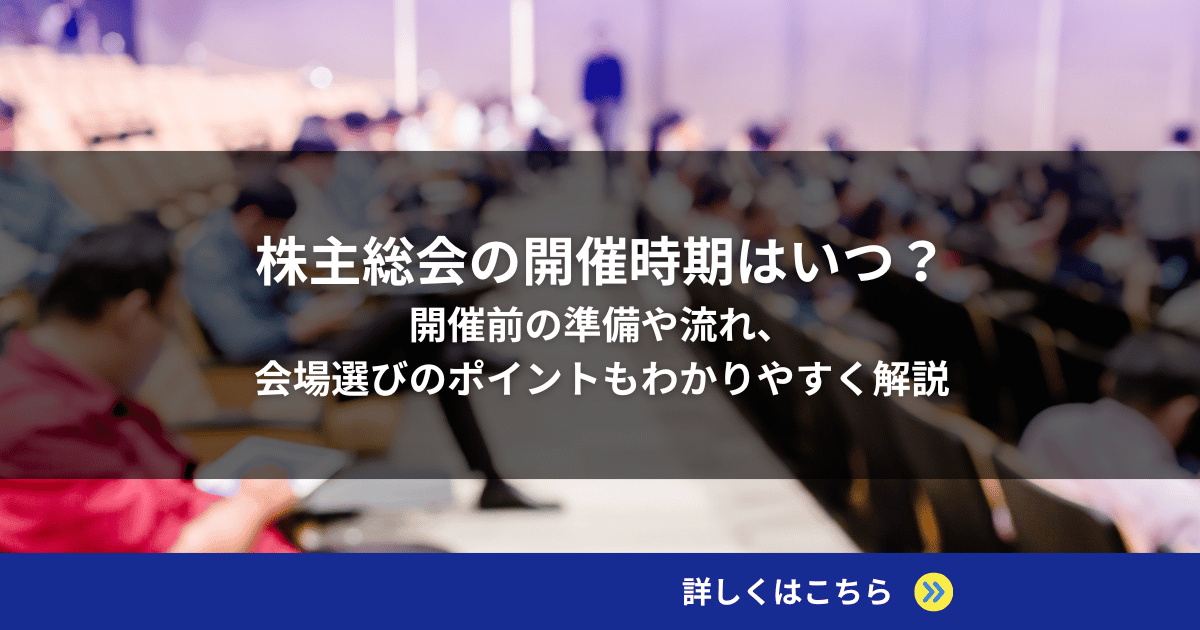【初心者向け】ワークショップの進め方|具体例とトラブル回避法も解説
「初めてワークショップを任されたけど、どう準備をすればいいの?」
「参加者が消極的だったらどうしよう」
「時間配分はどうすればいい?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
ワークショップを成功させるためには、事前の準備と進行のコツを押さえることが重要です。
準備から実施までの具体的な手順とトラブル対応を知っておくことで、参加者全員が活発に意見を出し合える、充実したワークショップを実現できます。
この記事では「ワークショップの準備から当日の進行までの流れ、よくあるトラブルの回避方法、他社の成功事例」まで、
現場で使える実践的なノウハウを具体的に解説していきます。
会場選びのポイントやリフレッシュメントの活用法なども含め、参加者満足度の高いワークショップの実現方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
都内でワークショップができる会場をお探しの方は【渋谷駅チカ】規模別イベントホール5選|セミナー・展示会に最適な会場を紹介をご覧ください。
目次
初めてのワークショップで不安に感じる3つのポイント
ワークショップの運営は、通常の会議の進行とは大きく異なります。
初めて担当する方にとっては、様々な不安がつきまとうものです。
まずは、よくある不安やその背景を理解することから始めましょう。
①参加者が積極的に参加してくれるか不安
よく聞かれる不安は、参加者の主体的な参加を促せるかです。
会議と異なり、ワークショップでは参加者同士の活発な意見交換や協働作業が不可欠です。
しかし、普段から密に連携していない部門間でのワークショップでは、参加者が消極的になりがちです。
「発言が少なくて議論が深まらないのではないか」「グループワークがうまく機能するだろうか」といった懸念は、多くの初任者が共有する不安点となっています。
②時間通り進行できるか不安
ワークショップの進行において、適切な時間管理は大きな課題です。
アイスブレイクから本題のディスカッション、まとめまで、複数のセッションで構成されるワークショップでは、予定通りに進行できるか不安を感じる方が多いものです。
各セッションで予定よりも議論が白熱し時間が超過したり、逆に思うように意見が出ず時間を持て余したりすることも少なくありません。
特に初めての運営では、どのセッションにどれくらいの時間を配分すべきか、また予定外の事態にどう対応すべきか、明確な基準を持てないことが不安の原因となります。
③期待する成果が得られるかが不安
ワークショップを開く際に気がかりなのが、実際にどのような結果が出せるのかでしょう。
「具体的な成果は上がるのだろうか」「参加者は満足してくれるのだろうか」こうした不安は、ワークショップの担当者なら誰もが感じているものです。
とりわけ、仕事の効率化や新しい企画を始めるためのワークショップでは、はっきりとした成果が必要なだけに、この心配は一層強くなります。
意見を出し合うだけで終わらず、実務に活かせる内容を引き出せるのか、また、参加者が「参加してよかった」と思えるような内容にできるのか。
こうした不安を抱える担当者は数多くいます。
このように、初めてワークショップを担当する方の不安は多岐にわたります。
しかし、これらの不安に対する対処方はあるのでご安心ください。
適切な準備と進行のコツを押さえることで、充実したワークショップの実現は十分に可能です。
そもそもワークショップの全体像を知りたい人は、ワークショップとは?会場選びと初めての開催で失敗しない3つのポイントを解説の記事もご覧ください。
ワークショップ準備で押さえるべき5つのポイント
効果的なワークショップの実現には、入念な事前準備が不可欠です。
初めてワークショップを運営する方でも、以下の5つのポイントを順に確認しながら準備を進めることで、充実したワークショップを実現できます。
具体的な準備のステップを見ていきましょう。
| ワークショップに必要な備品 |
|---|
|
1. テーマ設定:目的に合ったテーマを選ぶ
ワークショップの成否は、適切なテーマ設定から始まります。
参加者の興味を引き、具体的な成果が得られるテーマ選びが重要です。
まずは現状の課題を明確にし、具体的なテーマへと落とし込みます。
例えば「部門間の連携強化」という漠然とした表現ではなく、「営業部門とカスタマーサポート部門の情報共有における課題解決」のように、具体的な問題設定を行います。
また、参加者全員が意見を出せる範囲のテーマであることも重要です。
専門知識が必要すぎるテーマや、特定の部署にしか関係のないテーマは避け、誰もが当事者意識を持って参加できるテーマを選ぶとよいでしょう。
2. 参加者のリストアップと招待方法
ワークショップの質は、参加者の選定によって大きく変わります。
テーマに関連する部署から、適切な知識や経験を持つメンバーを選ぶことが重要です。
ただし、単に役職や経験年数だけでなく、積極的に意見を出せる人材を含めることで、議論の活性化が期待できます。
理想的な参加人数は、グループワークを効果的に行える規模を考慮して決定します。
一般的には、1グループ4-6名程度で、全体でも20名程度までが運営しやすい人数とされています。
これより多い場合は、複数回に分けての開催を検討しましょう。
招待の際は、ワークショップの目的や期待される成果を明確に伝えることが重要です。
事前に参加者の役割や準備すべきことを明確にすることで、当日のスムーズな進行につながります。
3. 必要な準備物と会場設備リスト
ワークショップを円滑に進めるには、適切な準備物と会場設備が欠かせません。
事前に必要なものをリストアップし、抜け漏れのないように準備を進めましょう。
| ワークショップに必要な備品 |
|---|
|
付箋は色分けによってアイデアの分類や優先順位付けを効率的に行えるため、複数の色を用意しておくのがおすすめです。
また、参加者に配布する資料やワークシートも忘れずに用意しましょう。
議論の土台となる現状データや、グループワークで使用するワークシートなど、事前に必要部数を確認し、余裕を持って準備することが大切です。
オンラインで実施する際には、共同編集可能なドキュメントツールやホワイトボード機能など、デジタルツールの活用も検討するとよいでしょう。
ただし、使用する場合は参加者全員が操作に慣れているか確認が必要です。
4. 余裕を持ったスケジュール作成
効果的なワークショップの実現には、適切な時間配分が不可欠です。
全体の所要時間を決めたら、各セッションの時間配分を検討していきましょう。
| 標準的なワークショップの時間配分(2時間の場合) |
|---|
|
ただし、これはあくまで目安であり、テーマの複雑さや参加者の人数によって調整が必要です。
重要なのは、各セッションに余裕を持たせることです。
予定よりも議論が白熱したり、逆に時間が余ったりすることを想定し、柔軟に対応できる余裕を持たせましょう。
例えば、2時間のワークショップなら、実際の進行予定は1時間45分程度で組み、残り15分を予備時間として確保しておくことをおすすめします。
5. 招待メールと事前共有資料の作成
参加者への効果的な情報共有は、ワークショップの成功を左右する重要な要素です。
招待メールには、開催目的、日時、場所といった基本情報に加え、ワークショップで取り組むテーマや期待される成果を具体的に記載します。
例えば、以下のような情報を含めると良いでしょう。
「本ワークショップでは、営業部門とカスタマーサポート部門の情報共有における課題を洗い出し、具体的な改善策を検討します。特に、お客様からのフィードバックを営業活動に活かすための仕組みづくりに焦点を当てます」
事前共有資料としては、現状の課題や関連データ、当日のタイムスケジュール、準備していただきたい事項などを含めます。
これにより、参加者が当日までに予めテーマについて考えを整理し、より充実した議論が可能となります。
スムーズな進行を実現する進め方のコツ3選
ワークショップの成功は、当日の進行方法によって大きく左右されます。
参加者が積極的に意見を出し合い、創造的な議論が展開されるよう、効果的なファシリテーションと柔軟な進行管理が求められます。
ここでは、実践的な進行のコツをご紹介します。
①参加者が積極的に議論できる場を作るファシリテーション術
ファシリテーターの役割は、参加者の意見を引き出し、建設的な議論を促進することです。
まず重要なのは、心理的安全性の確保です。
「間違った意見は存在しない」「どんな意見でも歓迎する」といったメッセージを、言葉と態度で明確に示しましょう。
具体的な声かけの例として、「○○さんの経験から、どのように感じられますか?」といった個別の問いかけや、「今の意
見に関連して、似たような経験をお持ちの方はいらっしゃいますか?」といった全体への投げかけが効果的です。
また、発言の要点を復唱したり、ホワイトボードに書き出したりすることで、意見が正しく理解され、尊重されていることを示します。
沈黙が続く場合は、2人組やグループでの小規模な対話から始めることで、発言のハードルを下げることができます。
「まずはお隣の方と2分ほど意見交換してみましょう」といった声かけで、徐々に全体での議論へと発展させていきます。
②ワークショップを活性化させるアイスブレイクのアイデア
アイスブレイクは、参加者の緊張をほぐし、活発な議論の土台を作る重要な役割を果たします。
本題に入る前の5-10分程度を使って、参加者同士が打ち解けられる雰囲気づくりを心がけましょう。
関係の質を高めるアイスブレイクの代表例では、「Good & New」があります。
「Good & New」は、参加者同士の心理的な距離を縮め、前向きな雰囲気でワークショップを始めるための効果的なアイスブレイク手法です。
それぞれの参加者が、最近あった「良かったこと(Good)」と「新しいこと(New)」を1つずつ共有します。
1人1分程度を目安に、全員が順番に発表を行います。
内容は難しく考えすぎる必要はなく、例えば、「Good:先週末に家族で海に行って、とてもリフレッシュできました」「New:今月から新しい趣味としてヨガを始めました」といった程度で問題ありません。
ファシリテーターが最初に自己開示の例を示すことで、参加者も話しやすくなるでしょう。
仕事に関することに限定せず、プライベートな話題も歓迎することを伝えると、より打ち解けた雰囲気が生まれます。
実施の際は、発表者以外のメンバーは相槌を打つなど、積極的に反応するよう促すのがおすすめです。
共感や興味を示すリアクションにより、参加者は自然と心理的な安全性が高まります。
心理的安全性が高まることで、和やかな雰囲気で意見を活発に交わせるようになり、本題での活発な意見交換や創造的な議論につながります。
③タイムキープの秘訣と柔軟な進行方法
時間管理は、ワークショップの質を保つ重要な要素です。
各セッションの開始時に所要時間を明確に伝えたり、残り時間を適宜アナウンスたりすると、参加者に時間への意識を手中させられます。
タイムキーパーになった人は、「あと15分でグループワークを終了します」「残り5分となりましたので、まとめに入りましょう」などのように声掛けを心がけましょう。
ただし、予定通りに進まないことも想定し、柔軟な対応も必要です。
議論が白熱している場合は、次のセッションの時間を調整して、重要な議論を途中で遮らないようにするのも必要です。
逆に、予定より早く終わった場合は、追加の問いかけや深掘りの時間として活用できます。
ただし、タイマーに縛られすぎず、議論の流れや成果の質を見ながら、適切なペース配分を心がけましょう。
ワークショップの進め方でありがちな失敗例
ワークショップ運営では、いくつかの典型的な失敗パターンが存在します。
失敗例とその対処法を事前に知っておくことで、より円滑な運営が可能になります。
本章では、特に初めての運営で起こりやすい失敗例と、その具体的な回避策をご紹介します。
| 失敗事例 |
|---|
|
失敗例1:参加者が消極的で盛り上がらない
参加者の消極的な態度は、ワークショップの最大の課題の一つです。
特によくある事象として、発言者が特定の人に偏る、質問を投げかけても反応が乏しい、グループワークでも会話が発生しないといった状況が挙げられます。
この状況を改善するためには、まず参加のハードルを下げることが重要です。
例えば、「正解・不正解」を意識させない問いかけを心がけます。
「この案の良い点を一つ挙げていただけますか?」といった形で、どんな意見でも受け入れられる雰囲気を作りましょう。
また、個人ワークを取り入れることも効果的です。
まず各自で考えをメモに書き出し、それをもとにグループで共有する形式にすることで、発言のハードルが下がります。
付箋を活用し、匿名での意見出しから始めることも有効な手段です。
失敗例2:話がまとまらずに時間オーバーする
時間オーバーは、特にワークショップ運営に慣れていないと起こりがちな問題です。
予定よりも議論が白熱したり、逆に議論の停滞で予定より時間がかかったりすることがあります。
この状況で慌てて進行を急ぐと、せっかくの議論が中途半端になってしまいます。
対処法としては、まず事前に「最低限達成すべき目標」と「余裕があれば取り組む項目」を明確に分けておくことです。
時間が押した場合は、核となる議論に集中し、付随的な議題は次回に回すという判断ができます。
また、グループ数が多い場合は、発表時間の調整も検討します。
全グループが詳細な発表を行うのではなく、特徴的な意見のみを共有し、詳細は後日文書で共有するといった方法も有効です。
失敗例3:脱線したまま議論を軌道修正できない
議論が白熱する中で、議論が本筋から外れてしまうのもよくある事例です。
特に、参加者が自身の経験や興味に引きつけて発言する中で、徐々に本来のテーマから逸れていくことがあります。
この場合、まず議論を遮る前に、その脱線した話題にも一定の価値があることを認めます。
「興味深い視点ですね。これは別の機会にぜひ深めたい話題ですが、今回のテーマに戻りましょう」といった形で、参加者の発言を否定せずに軌道修正を図ります。
ホワイトボードなどを活用して、本題から外れるものの、重要な指摘は記録として残しておくことも効果的です。
これにより、発言者は自身の意見が無駄にされていないと感じ、かつ本題への回帰もスムーズになります。
他社のワークショップ成功事例
実際に成果を上げた企業のワークショップ事例を学べば、自社での実践に活かせるヒントが得られます。
ここでは、特に効果的だった事例とそこから得られる視点をご紹介します。
| 他社の成功事例 |
|---|
|
成功事例1:充実した事前案内で円滑な進行を実現
NECマネジメントパートナーのオンラインワークショップでは、参加者への事前案内を重視しています。
研修内容の詳細な説明により、参加者は必要な準備を整えて臨むことができるようです。
ワークショップでは、通常の会議やセミナーと異なり、参加者同士の活発な意見交換が不可欠です。
そのため、カメラとマイクの使用を必須としています。
画面音で顔が見えるからこそ対面のワークショップに近い、臨場感のある環境を作り出すことができます。
ただし、オンラインツールの利用に不安を感じる参加者もいるため、事前にカメラやマイクの使用が必要であることを明確に伝えることが重要です。
また、明確な参加対象者を定めていることで、参加者の知識レベルが揃い、より効果的な進行が可能になります。
| 社内ワークショップで活かせるポイント |
|---|
|
成功事例2:次世代エンジニアの育成プログラム
革新的なサイクロン掃除機を世界で初めて開発したダイソンは、ジェームズダイソン財団を設立し、未来のエンジニアを育成する教育支援プログラムを展開しています。
その中で取り入れられたのが、中学生を対象とする「問題解決ワークショップ」です。
ワークショップでは生徒たちがエンジニアとして、グループワークを通じて問題解決に取り組む内容になっています。
実際にモノに触れながらロジカルシンキングを学べたり、エンジニアのデザインプロセスを学べたりするため、現場で活躍するエンジニアの視点や考え方に触れられ、具体的な働く現場のイメージをしやすく深い学びにつながります。
社内で部署横断的なワークショップを行う際にも、このような実践を通じて他部署の業務を体験してみることで、部署間の
相互理解を深め、連携強化に役立てられるかもしれません。
成功事例3:業務改善ワークショップ
サイボウズは、クラウドウェアサービスの提供に加えて、業務改善の基礎を学ぶワークショップを展開しています。
このワークショップでは、参加企業が自社の業務の現状を把握し、具体的な課題を抽出するプロセスを体験できます。
単なる商品販売ではなく、まず業務改善の必要性と基本的なアプローチを理解してもらうことで、より効果的な提案につなげている事例です。
自社商品の販売前に、課題認識の機会を設け、その解決手段として自社商品の利用を促すといった対外向けのワークショップの開催も有効でしょう。
社内においても、業務改善のためにはまず課題の共通認識が重要なため、参加者全員が当事者意識をもって取り組める環境づくりと、その為の解決手段を考える機会の提供が効果的でしょう。
会場選びとリフレッシュメントで満足度アップ!
ワークショップの成功には、適切な会場選びも重要な要素です。
参加者が集中でき、活発な議論が行える環境づくりは、成果を大きく左右します。
また、適切なリフレッシュメントの提供は、参加者の満足度と集中力の維持に大きく貢献します。
例えば、自然光が入る会場は参加者の集中力維持に効果的で、開放的な空間はアイデア創出に役立つでしょう。
他にも、リフレッシュメントの提供も、ワークショップの質を高める重要な要素です。
水分補給用のお水やお茶は常時用意し、午前中のワークショップではコーヒーや紅茶、午後のセッションではスイーツなども用意すると、参加者の満足度が高まります。
当社の「会場探しコーディネーター」にご相談いただければ、これらの要件を満たす最適な会場をご提案いたします。
イベント会場運営に詳しい担当者が、予算や参加人数、目的に応じた会場を提案し、ケータリングサービスの手配までワンストップでサポートいたします。
さらに、ご紹介する施設は当日の設営や機材トラブルにも迅速に対応可能なため、運営担当者は本来の業務であるファシリテーションに集中できます。
ワークショップの運営でお困りの際は、ぜひ会場探しコーディネーターにご相談ください。
都内でワークショップができる会場をお探しの方は【渋谷駅チカ】規模別イベントホール5選|セミナー・展示会に最適な会場を紹介をご覧ください。
Pick Up
関連記事