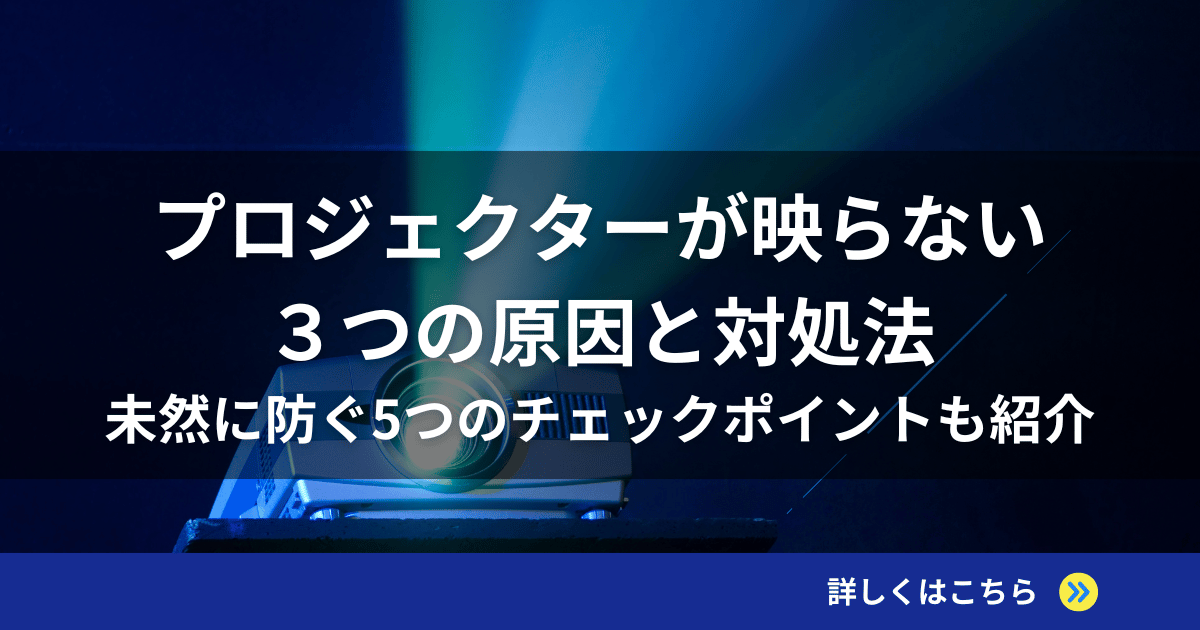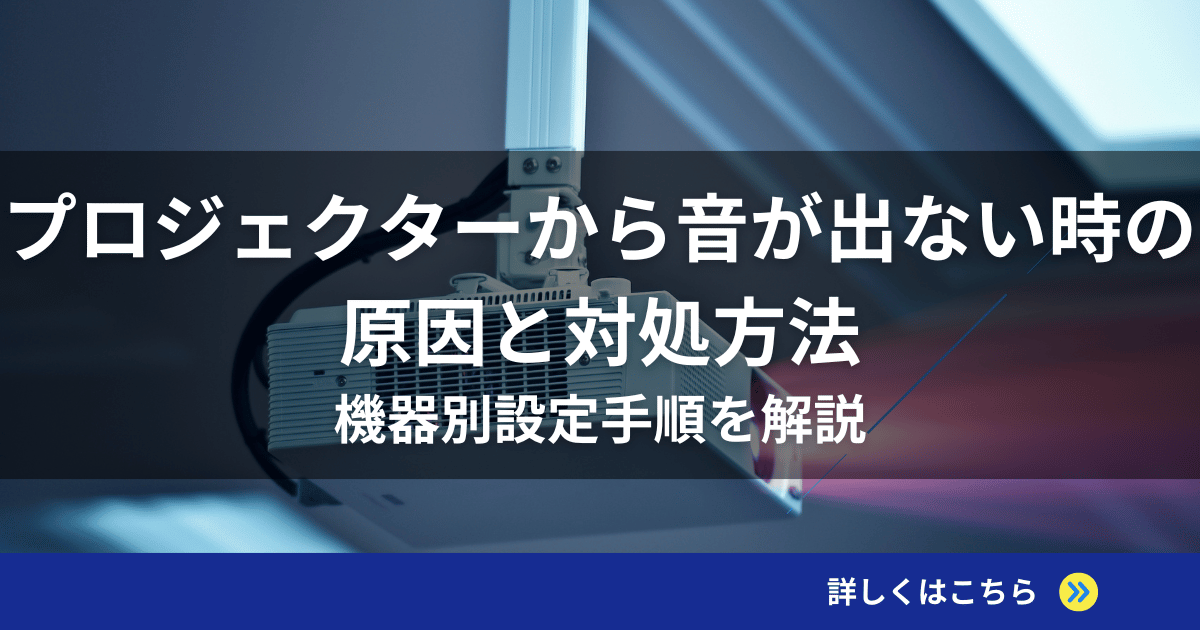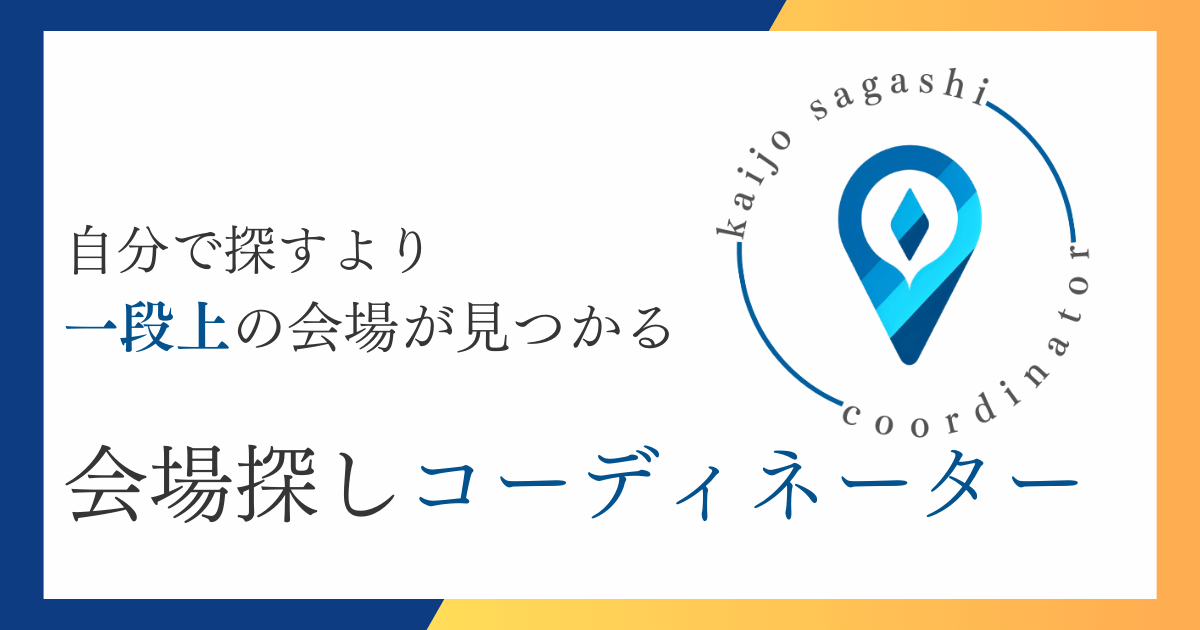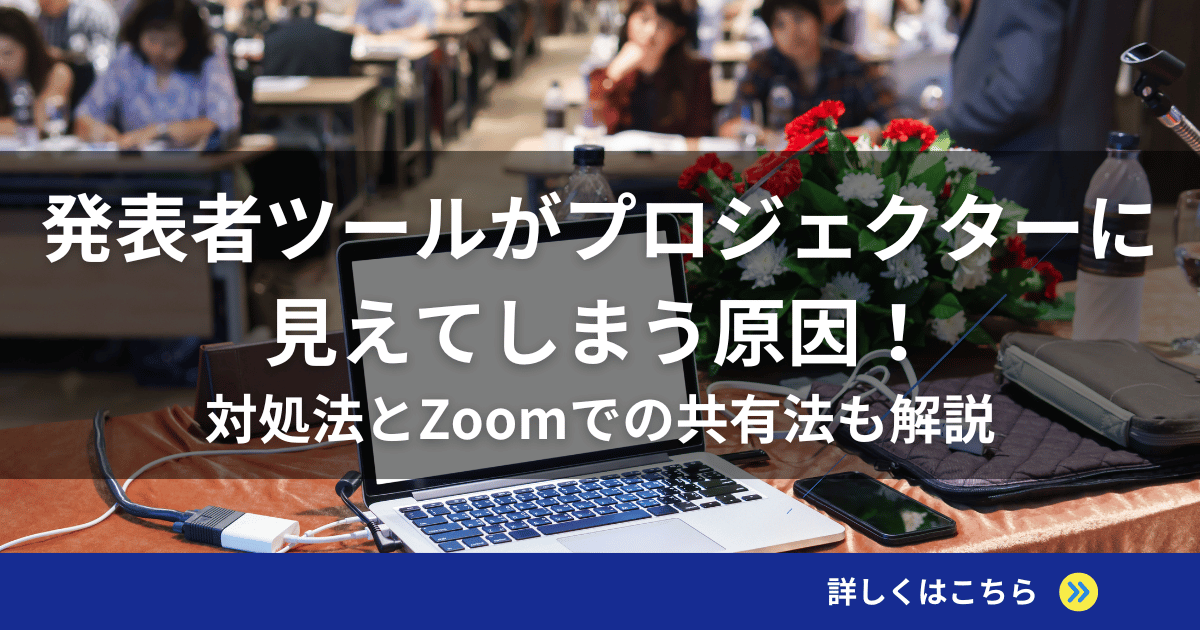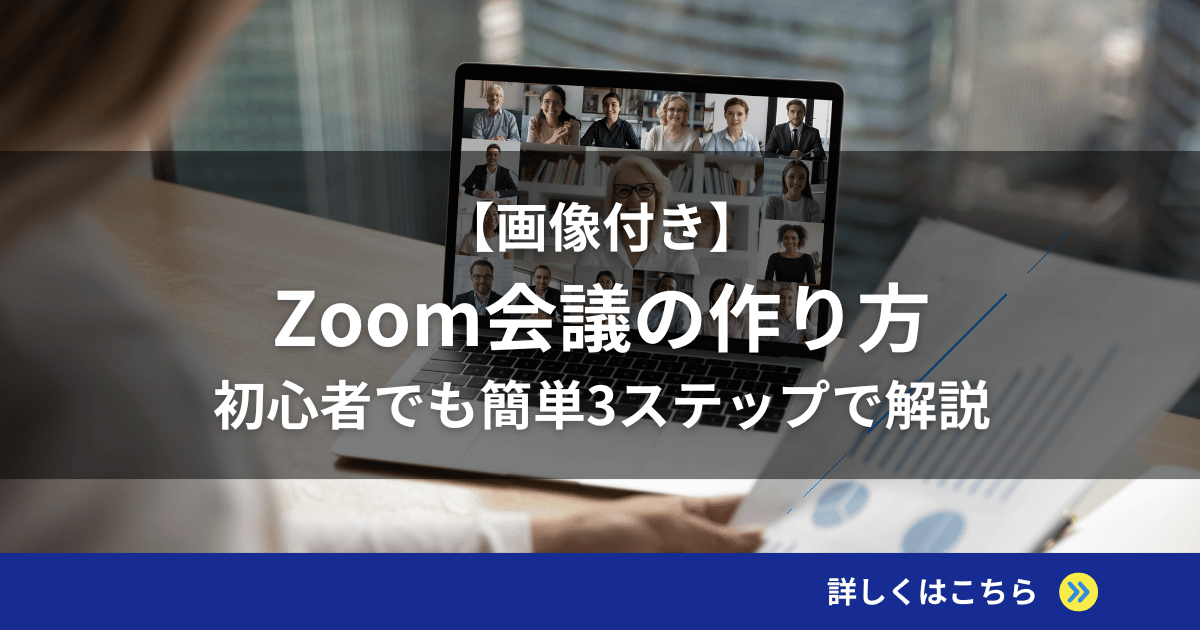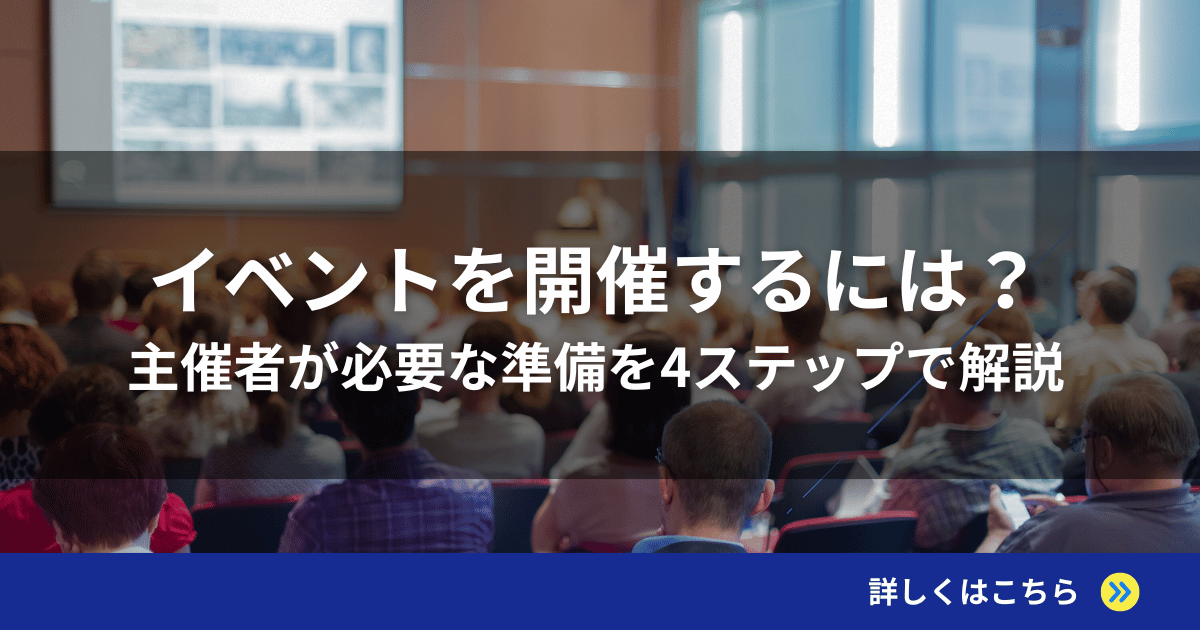イベント中のトラブルに強くなる!会場視点で学ぶ緊急時対応マニュアルの作り方
イベント運営は、多くの人の協力と細かい準備が必要ですが、それでも予期せぬトラブルが発生することがあります。
「何から手をつければいいのか分からない…」「緊急時にパニックになりたくない」と不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、イベント運営中に起こりがちなトラブルの種類とその解決策をわかりやすく解説。
さらに、トラブルに備えるための「緊急時対応マニュアル」の具体的な作り方を7つのステップで紹介します。
この記事を読むことで、どんな状況でも落ち着いて対応できる自信を手に入れましょう!
目次
イベント運営で起こりやすいトラブル例

イベント運営では、予想外の事態で何か知らのトラブルが発生するものです。
しかし、事前にトラブルの事例を知っておけば、対処することができます。
ここでは、イベント実施の際によく発生するトラブル例について紹介します。
① 機材トラブル
イベント運営で最も多い問題の一つが、映像や音響、照明などイベントで使用する機材に関するトラブルです。
たとえば、プロジェクターが急に動かなくなったり、マイクからノイズが発生したりするケースが挙げられます。
このような機材トラブルの原因は、接触不良やバッテリー切れ、設定ミスなどさまざまです。
機材を自分たちで用意する場合は、事前に動作チェックを行ったり、予備の機材を用意したりと、万全な準備をしておくのが大切です。
また、イベント当日には専門の技術スタッフに依頼することで、問題が発生した際にも迅速に対応できるような体制作りも検討するとよいでしょう。
具体例として、映像関係のトラブルについてまとめた記事もありますので、具体的な対処法を知りたい人はこちらもぜひご覧ください。
② 出演者トラブル
急な病欠や天候や交通トラブルなどによる遅刻など、イベントに登壇される出演者のトラブルも運営者にとって大きな課題です。
特に基調講演や重要なセッションを予定している場合、出演者の欠席は全体の進行に大きな影響を及ぼします。
代役を立てる方法もありますが、リモート参加できるような環境を整えておくのも1つの手段です。
講演家の方の実例として、地方公演への移動中にトラブルが発生し会場に間に合わなくなった方がいました。
しかし移動中にリモート登壇に切り替えたことで、イベントに穴をあけず、予定通り進行できたケースがあります。
このようなトラブルへの対処も踏まえ、スケジュールを柔軟に調整できるような余裕を持たせておくことで、影響を最小限に抑えられます。
③ 天候トラブル
屋外イベントでは、悪天候による中止や変更が避けられない場合があります。
特に、台風の影響などによる雨や強風は、来場者の安全にも影響を及ぼすため、注意が必要です。
考えられる対策としては、雨天時の代替実施方法を先に検討しておくことです。
屋内別施設の確保や、テントの設置など、雨が降っても続行できるような体制を整えておくと安心でしょう。
また、台風などの場合には、事前に中止判断の基準を設定し、関係者へ共有しておくのが重要です。
加えて、強風時の対策として、「風速〇m以上になったらテントをたたむ」「イベントの中止判断をする」などの条件は会場によって異なる場合があります。
必ず事前に会場担当者と条件をすり合わせ、安全に実施できるような体制を整えておきましょう。
④ 参加者や近隣からのクレーム
イベントで多くの来場者が見込まれる場合、案内不足等による参加者の不安や、混雑や騒音などによる近隣住民からの苦情などが考えられます。
このような問題は、イベント全体の評判を左右することとなり、今後のイベントの継続可否に関わります。
イベント会場を借りる場合は、事前に来場者動線をシミュレーションし、混雑を最小限に抑えるような工夫が必要です。
当社の運営している施設では、スポーツ関連商品のイベントの際に長蛇の待機列が発生することが予想されたため、事前の整理券配布を実施するなど、主催者に工夫をしていただいた事例があります。
このように、特に複合施設のイベントスペースなどの場合、施設内の他の店舗などへの影響も考慮が必要です。
周辺住民や施設関係者などには、事前に情報共有をするなどによりイベントへの理解を求めつつ、必要に応じて協力体制を整えるのが重要です。
⑤ 火災・地震など災害トラブル
火災や地震などの災害トラブルは、イベントとは関係なく突然発生するものです。
イベント運営中に発生した場合、多くの来場者を含めた安全確保が最優先となるため、速やかな避難指示を出す準備が必要です。
イベント規模によっては、自衛消防組織という管理体制を敷き、全体統括、消防等への通報、避難誘導、応急救護など、役割分担をして、有事の際に迅速に行動できるようにします。
イベントホールの利用の際には、組織図の提出が必須となっている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
また、イベント当日には実際の避難経路を把握しておき、会場設営の際には避難経路にモノを置かないなど、万が一の際に逃げ遅れることの無いよう、全スタッフで把握しておくのが大切です。
事前準備でイベントトラブルの8割は防げる

トラブルの多くは、事前準備の段階で予防できます。
特に初めてイベント運営を担当する場合、準備不足がトラブルを招く原因となりがちです。
適切に準備しておかないと、機材や設備の不具合、参加者の案内が不明確、天候変化による予期せぬトラブルなど、様々な問題に迅速に対応できません。
しかし、事前にトラブルを想定しておくことで「予測外の問題」を最小限にできます。
対策としては、イベント運営に必要なタスクをすべて網羅したチェックリストを作成するなどが効果的です。
他にも、雨天が予測される場合に屋内施設を確保しておけば、当日の混乱を防げます。
想定できる問題には対策を、想定外の事態には代替案を用意しておくことが重要です。
緊急時対応マニュアルの作り方7ステップ

イベントにおけるトラブルシューティングをまとめた緊急時対応マニュアルは、トラブルが発生した際に冷静かつ迅速に行動するための「指針」となるものです。
以下の7ステップを実践することで、ほとんどのケースで対応できる準備が整います。
イベント準備の際は1つずつ意識してみてください。
ステップ1: 想定されるトラブルを洗い出す
まず、イベントの種類や規模に応じて、想定されるトラブルをできるだけ多くリストアップします。
具体的には、以下のような内容です。
- 機材不良:プロジェクターが動作しない。
- 参加者の急病:救急車を呼ぶ必要がある場合。
- 災害:地震や台風による中止対応。
トラブルを洗い出す際は、軽微なものだけでなく「最悪の事態」を考え、それに備えることが重要です。
ステップ2: トラブルごとの対応手順を決める
次に、洗い出したトラブルごとに、以下のように対応手順を具体的に記載します。
- 機材不良:代替機材を用意→技術スタッフに報告→会場担当者と連携。
- 参加者の急病:応急処置を実施→救急車を手配→緊急連絡先に通知。
具体的な対処手順が明記されていれば、現場レベルのスタッフでも冷静に対処可能です。
また、当日初めて現場に入るアルバイトスタッフも、マニュアルを読めばどこまでは自分で判断してよいのかも明確になり、安心して現場に臨めます。
ステップ3: 緊急時の連絡フローを設計する
イベント中にトラブルが発生した際には、内容によって判断する人が変わります。
連絡・指示系統を明確にしておくことで、迅速にトラブルへの対応が可能になります。
現場スタッフから現場責任者、そして主催者へ連絡するなど、最終的に誰が判断するのか、はっきりさせておくと安心です。
また、必要に応じて会場担当者との連携体制を整えておくことも重要です。
ただし、盗難や物損事故、急病人の対応など、警察や消防への連絡が必要な事態では、「人命最優先」で現場判断で緊急連絡をするように全スタッフへ共有しましょう。
ステップ4: 役割と責任を割り振る
緊急時の対応で混乱しないためには、各スタッフの役割を明確にしておくことが重要です。
例えば、運営責任者は全体の指揮をとり、司会者は会場の混乱を避けるために進行を止めずに場をつなぐ、などが挙げられます。
また、技術スタッフには機材トラブルの対処など、ポジションごとに専門性を要する場面も想定されます。
想定されるトラブルごとに、適切な担当者を配置するのが重要です。
役割と責任分担を明確にしておくことで、責任の所在があいまいにならず、迅速な対応が可能になります。
ステップ5: 緊急連絡先と必要ツールを用意する
連絡系統や役割を設定したら、緊急連絡先のリストや緊急対応用の備品などを準備します。
連絡先は、各ポジションの責任者の携帯電話や、警備会社、消防、近隣の医療機関などをひとまとめに確認できるようにしましょう。
また、大きな会場では直接連絡が取れる手段として、無線機を用意したり、応急救護セットを本部に用意しておくと安心です。
なお、無線機は、緊急時の連絡をスムーズにするために、主催者用と運営スタッフ用、技術スタッフ用など、必要なセクションによってチャンネル系統を変えておくのがおすすめです。
ステップ6: シミュレーションで運用テストを行う
可能であれば、想定シナリオを作成し、全スタッフで対応訓練するのが望ましいです。
イベント規模や内容によっては、消防から必ず実施するように求められるケースもあります。
実際の動きに即した訓練をすることで、事前に運営フローの問題点を洗い出すことができるため、本番時の実際の対応がよりスムーズに改善できます。
予算やスケジュールの都合上難しい可能性はありますが、実際に体感してみないとわからないことも多くあるため、少なくとも運営責任者クラスの間ではシミュレーションできる状況を整えるのがおすすめです。
ステップ7: マニュアルを簡潔にまとめて共有する
緊急対応フローがまとまったら、マニュアルに簡潔にまとめて、全スタッフへ共有しましょう。
特に「誰でもすぐに使える」状況であることがポイントです。
イベント全体のマニュアルもあるため、細かな情報もすべて記載してしまうと、必要な情報を網羅できないだけでなく、読まれない可能性もあります。
要点を簡潔にまとめて、発生したトラブルに応じて、誰が何をすればいいのかを明確にしておくのが重要です。
イベントトラブルには会場担当者との連携が欠かせない

イベントホールや会場は、多くの場合複合施設の一部として運営されており、関係者が多岐にわたるため、トラブル対応には会場担当者との連携が不可欠です。
特に緊急時の中止判断や災害時の避難対応では、施設側の協力が重要になります。
| 会場担当と事前に確認すべきポイント |
|---|
|
会場担当者との連携をスムーズにするためには、連絡窓口を一本化し、緊急時にどこに連絡すればいいかを明らかにしておきましょう。
また、大規模なイベントほど事前の打ち合わせが重要で、当日のスケジュールや緊急対応の際のプランをすり合わせておくことが重要です。
会場担当者との強固な連携は、トラブル対応のスピードと的確さを左右します。
有事の際も安心できるイベント会場を見つけたい方は、イベント会場レンタルで失敗しない選び方の記事もご覧ください。
イベントトラブルを防ぎ、成功するイベント運営を目指そう

イベントトラブルは、事前準備や適切な対応策を講じることで多くを防ぐことができます。
また、緊急時対応マニュアルを作成しておくことで、万が一の際にも冷静に対処できるようになります。
トラブルへの備えは、参加者や関係者の信頼を得るためにも非常に重要です。
| この記事のポイント |
|---|
|
上記のポイントを参考に、まずはトラブルの洗い出しから着手することをおすすめします。
また、イベント運営の経験が少ない場合や、対応に不安がある場合は、専門家のサポートを検討されるのも一つの方法です。
当社では、イベント会場に精通した「会場探しコーディネーター」によるコンサルティングサービスを提供しています。
会場の特性を熟知したスタッフが、イベントの事前準備からトラブル対策まで丁寧にサポートいたします。
プロの視点からのアドバイスにより、イベント運営の負担軽減にお役立てください。
ご相談は無料で承っております。
トラブルを未然に防ぎ、万一の際も適切に対応できる体制を整えることで、安心してイベント運営に集中できる環境づくりをサポートいたします。

「自分にぴったりの会場がどれかわからない…」
”会場のプロ”がおすすめする会場を見てみませんか?
まずは無料で会場を見てみる
Author Profile
会場探しコーディネーターメディア編集部
運営会社:株式会社シアターワークショップ
“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。
最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。
本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。
▼お問い合わせフォーム▼
会場探しのご相談はコチラ
Pick Up
関連記事
プレゼンや会議で突然「プロジェクターが映らない!」という事態に直面したことはありませんか?