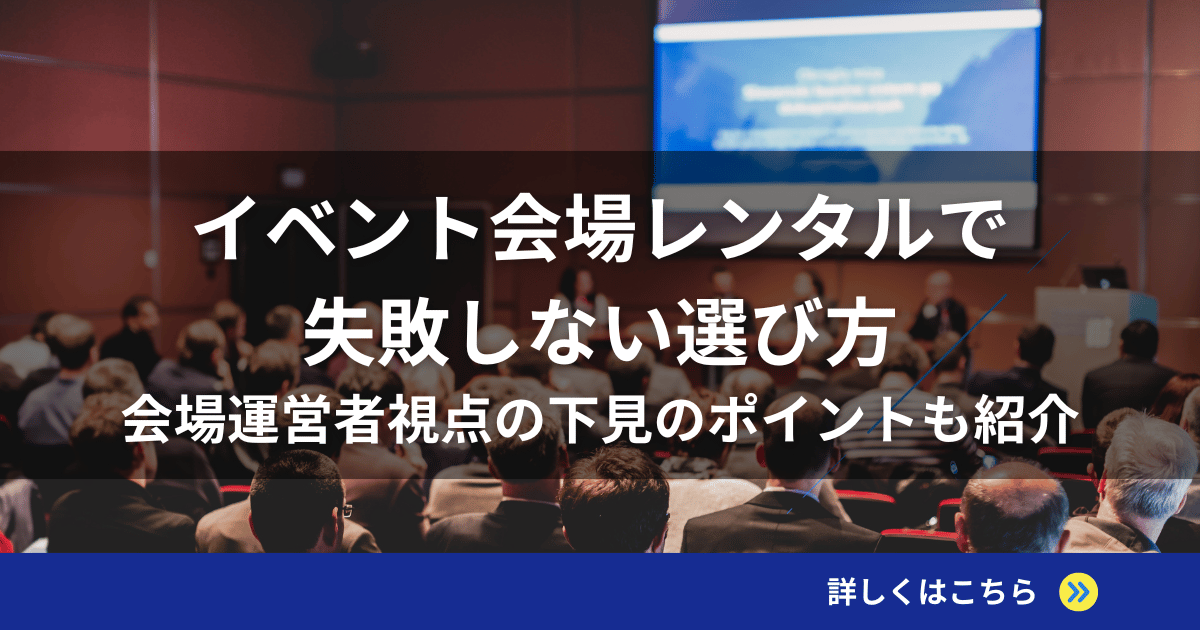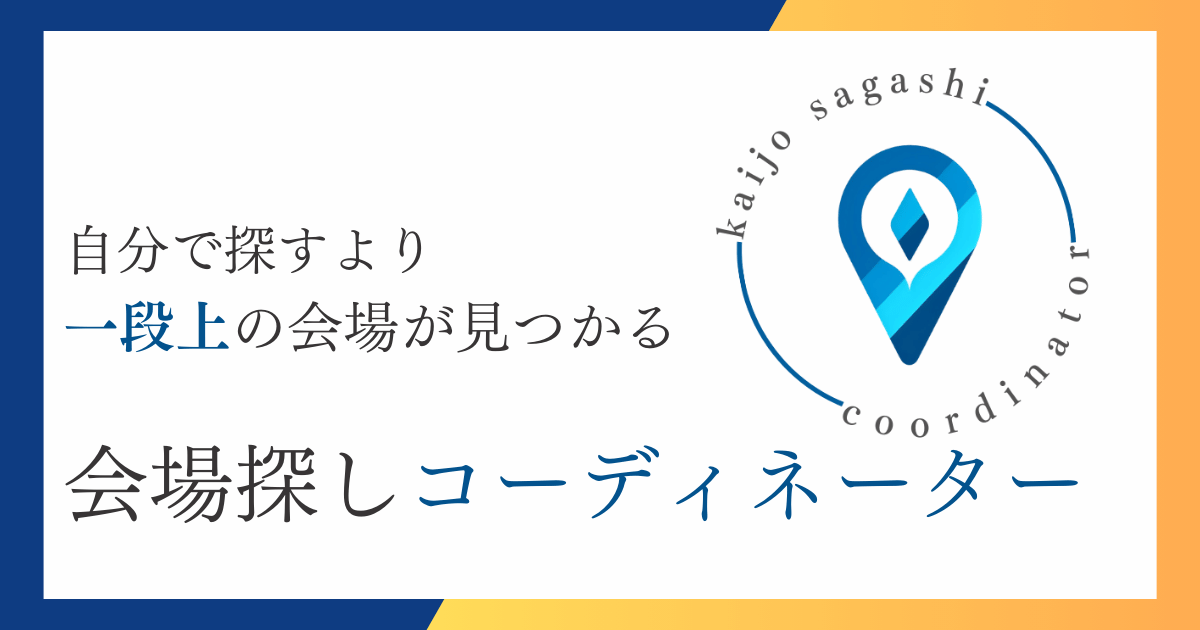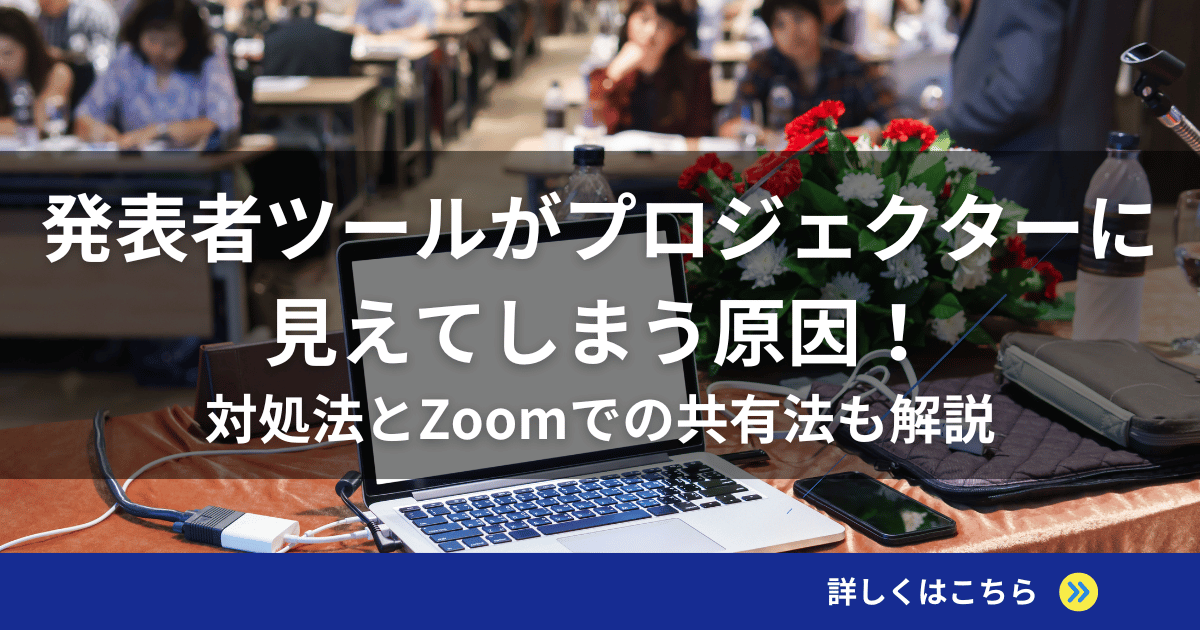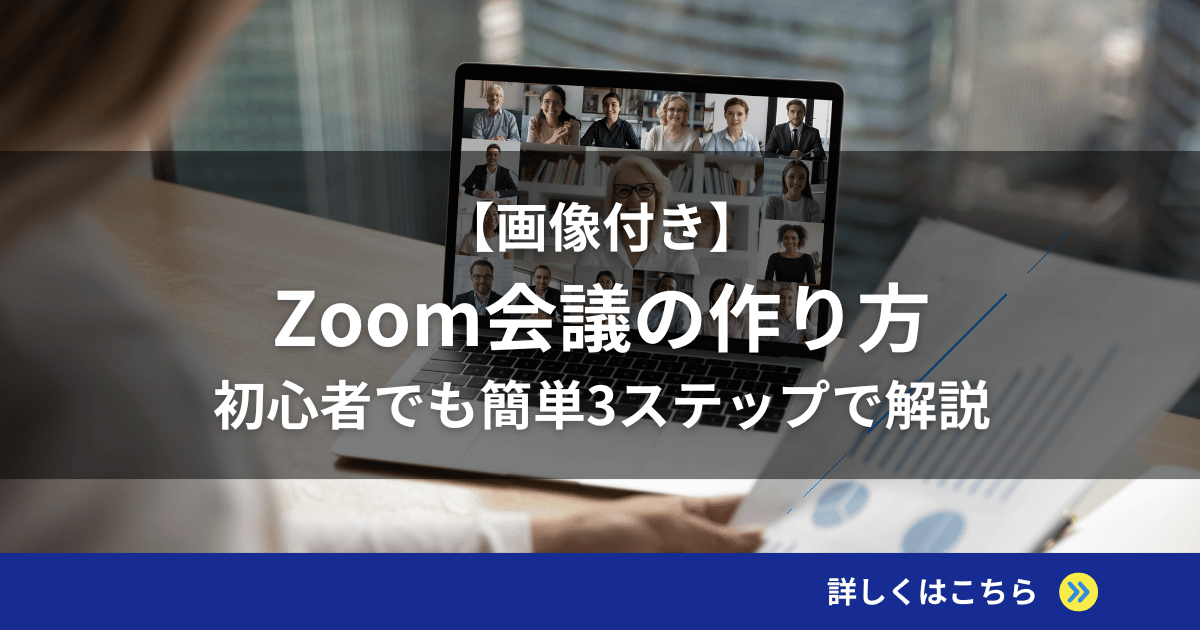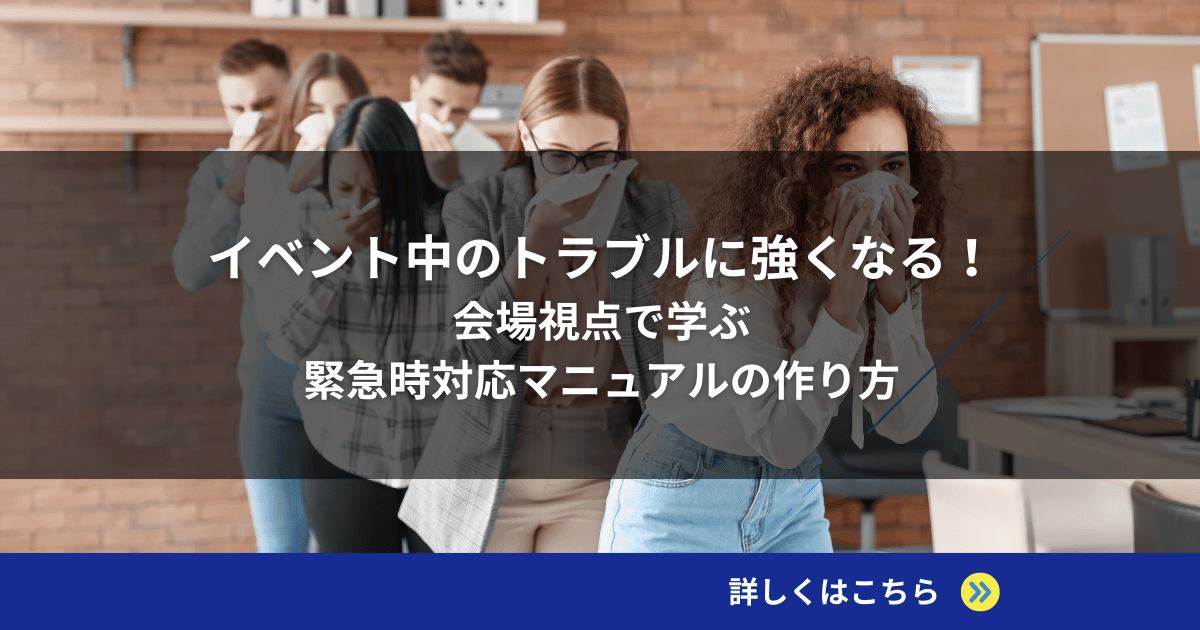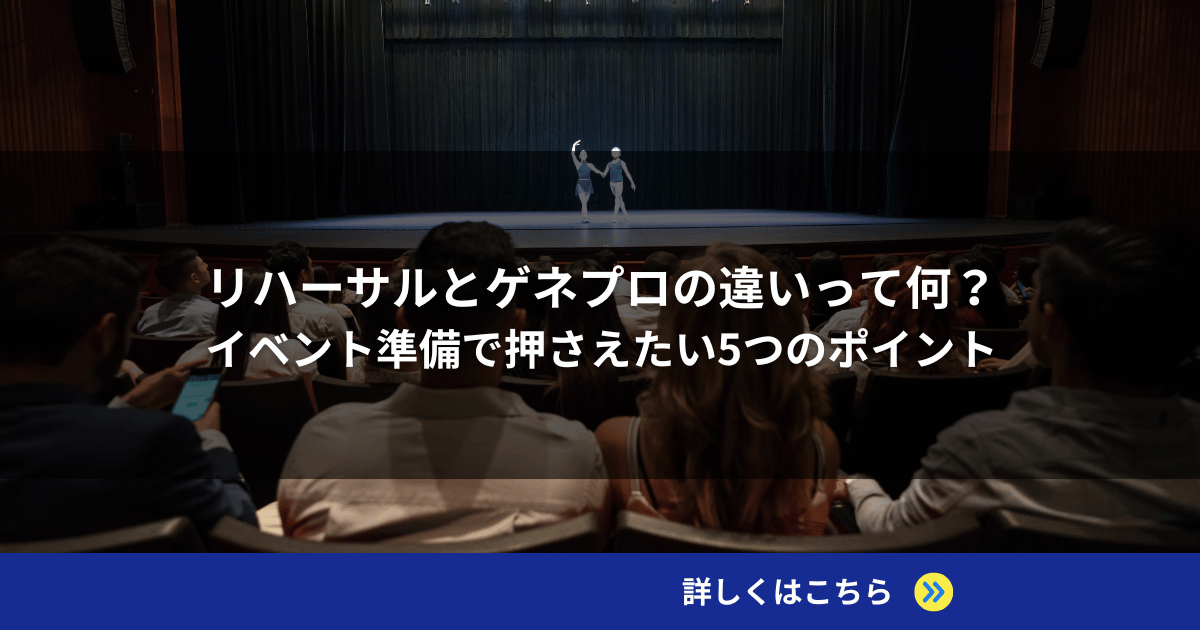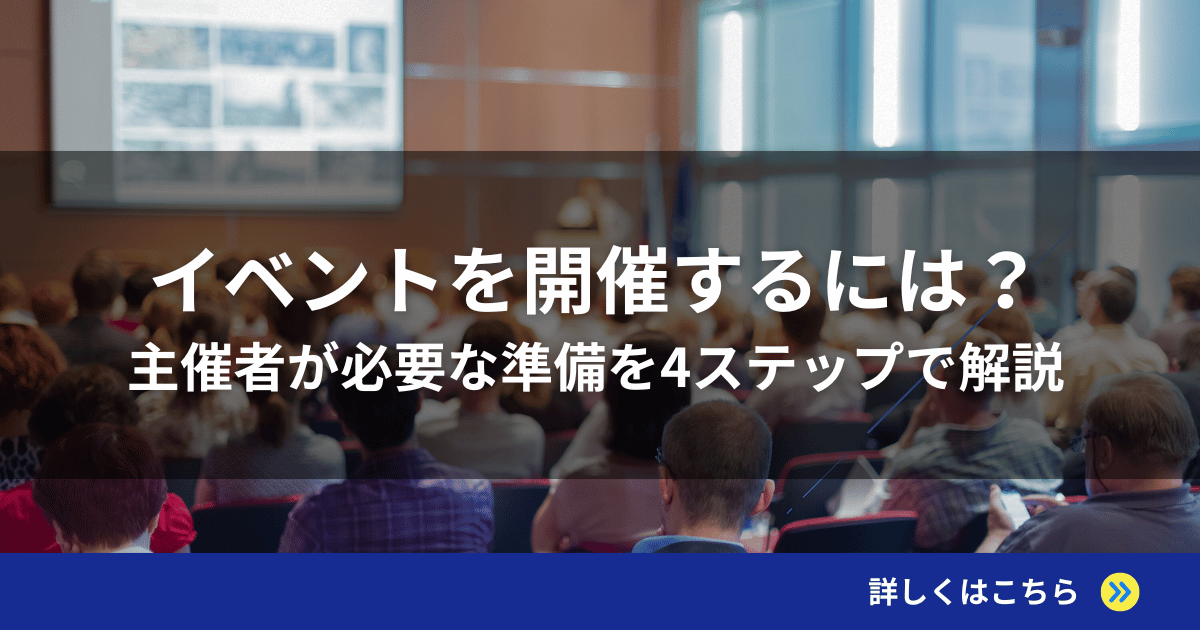イベント段取りと運営マニュアルの作り方!今すぐ実践に役立つポイントも解説
会社で初めてイベントを任されて不安を感じていませんか?
イベントを成功させるためには、事前の準備が何より大切です。
特に、段取りを整理し、関係者全員が共有できる運営マニュアルを作ることで、当日のトラブルを防げます。
この記事では、「イベントの準備から運営マニュアルの作り方まで、現場で役立つポイント」をまとめました。
経験豊富なイベント会場運営スタッフの知恵を集めた内容なので、きっと皆さんのお役に立てるはずです。
イベントの段取りをする中で、会場選びに迷われたらイベント会場レンタルで失敗しない選び方|会場運営者視点の下見のポイントも紹介の記事もご参考にされてください。
目次
イベントは「段取り8割」といわれる理由
イベントの成功は、事前の段取りで8割が決まると言われており、イベント現場のプロたちが入念に準備を行うのには理由があります。
当日の突発的なトラブルなど、予期しない事態が発生した場合、その場での対応には限界があり、取り返しのつかないミスや遅延が発生する可能性が高いからです。
全体のスケジュールから備品手配、スタッフの役割や配置決めなど、事前に決めておくべき項目は多岐にわたります。
特に初めてイベントを担当する方は、準備に十分な時間を確保するのが大切です。
イベントの段取り不足で起こりがちな失敗3選
イベント運営の現場では、思いもよらないところでトラブルが発生するものです。
特に準備が十分でない場合、小さなミスが大きな問題に発展しかねません。
ここでは、実際のイベント現場でよく起こる失敗例とその対策を紹介します。
これらの事例を知って対策しておけば、イベントでの失敗を回避できる可能性がぐっと高まるでしょう。
①必要な備品の手配漏れ
イベント実施に必要な備品が揃っていないと、当日の進行に大きな支障をきたします。
例えば、プレゼンテーション用にPCを持ってきたが、Macのためプロジェクターに接続するための変換機が必要だったことを当日に知り、急いで買いに走るなどの事例はしばしば起こっています。
こうしたトラブルを防ぐには、備品リストの作成が欠かせません。
また、一人でリストを作成すると抜けもれが発生する原因となるため、必ず複数名でダブルチェックを実施するなど、見落としを防ぐ対策が必要でしょう。
②曖昧な進行で大幅な時間オーバー
イベントはあらかじめタイムスケジュールを細かく組んでおかないと、大幅に時間オーバーすることがよくあります。
特に複数のプログラムが連続するようなイベントでは、1つの遅れが後の進行に大きく影響します。
例えば、講師や登壇者に時間配分などを事前に説明しなかったために、当日話が盛り上がりすぎて30分オーバーし、後のプログラムを短縮せざるを得ない状況になる可能性もあります。
また、休憩時間の設定が短すぎて、次のセッションまでに参加者が戻ってこれないなどのトラブルも起こりがちです。
イベント関係者に周知するためにも、具体的な進行表や全体のタイムテーブルを作成しましょう。
スケジュールを作成する際は、移動や準備などを考慮した予備時間を十分に確保するのが大切です。
また、組んだスケジュールで実際に問題なく進行できるかどうかは、リハーサルでも確認するようにしましょう。
③指示系統が不明確で運営スタッフが混乱する
イベントでは思った以上に多くの人が関わります。
そのため、指示系統がはっきりしていないと、運営スタッフは誰に確認をしたり、報告したりすべきかの判断がつかず、混乱を招いてしまいます。
例えば、指示者が不在のためにスタッフ間での情報共有が適切に行われず、同じ作業を複数人で重複して実施してしまったり、反対に必要な対応が行われないなどのトラブルが発生してしまうおそれがあるでしょう。
他にも、トラブル時のエスカレーションが曖昧だと、一次対応にあたるスタッフが不安に感じたり、適切な指示を仰げずに状況を悪化させてしまうリスクもあります。
マニュアル作成時に組織図の作成と担当業務の明確化、緊急時の対応フローなどを明記し、事前のスタッフミーティングでの周知が必要でしょう。
運営マニュアルに入れるべき内容11選
運営マニュアルをしっかりと作りこんでおけば、当日の運営スタッフたちがどのように動くべきかが明確になります。
関係者全員が同じ情報を共有し、統一された基準で動けるためです。
イベントの運営マニュアルを作成する際は、以下の11の要素を含めるとよいでしょう。
| 概要 |
|---|
|
1.概要
イベントを円滑に進めるには、まず概要をしっかりと整理することが大切です。
目的や規模、全体の流れといった基本情報が、すべての準備計画の基礎となります。
記載すべき内容は、開催日時、場所、参加予定人数などの基礎情報に加え、主催者の意図や開催趣旨も含めます。
例えば「新商品発表会では、商品特徴の説明よりも、実際の使用感を体験してもらうことに重点を置く」といった具体的な方向性まで盛り込むと良いでしょう。
なお、これらの情報は単なる箇条書きだけではなく、開催趣旨については文章形式のほうがイベントの目的や主催者の意図を、関係者全員がより深く理解できます。
2.組織図
組織図は、イベントに関わるメンバーの役割や指示系統を一目でわかるようにするための資料です。
特に誰が責任者で、判断する人なのかを明確にし、スタッフ全員がトラブル発生時に「だれに相談・報告すべきか」を把握できるようにしておく必要があります。
セミナー運営などであれば、統括責任者、受付担当、会場設営担当、進行管理担当など各部門の責任者を配置し、その下にチーフ、スタッフなどの階層構造を作っておくのが一般的です。
組織図があれば、機材トラブルや来場者の体調不良など、緊急事態が発生した場合でも、すぐに適切な担当者へ連絡できます。
また、判断が必要な場面でも決裁ルートが明確であるため、スピーディーな対応が可能です。
3.タイムテーブル
詳細なタイムテーブルは、イベントの時間管理における最重要ツールです。
準備から撤収までの全工程を時系列で示すことで、各担当者が自身の役割のタイミングを正確に把握できるためです。
実践的なタイムテーブルでは、設営開始から撤収までの全ての作業を15分単位で記載し、各時間帯での実施項目、担当者、注意点を明確にします。
タイムテーブルを組む際には、予期せぬ遅延に対応するため、必ず予備時間も設定しておく必要があります。
4.会場見取り図
会場のレイアウト図は、会場の利用計画の基礎であり、スムーズな運営には欠かせません。
机や椅子、設備・備品の配置を図面上で検討することで、限られたスペースを最大限に活用できます。
特に重要なのは、人の動きを想定した動線の確保やスタッフの配置です。
参加者の移動経路とスタッフの作業動線は区別して描き、人の動きがわかりやすい表現を心がけましょう。
100人を超えるような大規模なイベントでは、通路幅に特に注意が必要です。
主要な通路は最低でも2メートル幅を確保し、撮影スペースや荷物置き場は人の流れを妨げない場所に配置します。
こうした細かな配慮が、当日の混雑や事故防止につながります。
5.サイン計画
会場案内用のサインは、参加者が迷わずに目的地にたどり着けるかを左右する重要なポイントです。
多くの場合、イベントの参加者は初めてその会場へ訪れます。
受付やトイレの位置、会場マップなど、参加者の視点に立ち必要な誘導サインを計画しましょう。
遠くからでも視認できるサイズにする、曲がり角や動線が分かれる箇所には必ず設置するなど、細やかな配慮が必要です。
特に大規模な会場では、天井から吊るせるケースもあるため、来場者の動線阻害にならずに効果的な案内看板を設置できます。
6.スタッフ配置図
当日のイベントをスムーズに運営するには、適切なスタッフの配置が欠かせません。
各エリアに必要な人数を配置、全体をカバーできているかどうかを考慮して計画を立てましょう。
具体的には、受付の人数は足りているのか、誘導スタッフは十分か、入場時や本番中、終了後の参加者の流れに沿って、必要な人員を配置します。
また、誰がそのエリアの責任者なのかなども明確にしておくと、当日担当するスタッフも迷わずに済みます。
なお、必要なポジション数ぎりぎりでスタッフを用意するのではなく、休憩要員も考慮した人員計画が大切です。
7.持ち場ごとの作業フローや作業内容
イベント運営に関わるスタッフの多くは、担当する持ち場の情報を中心に確認します。
各スタッフが持ち場の役割をしっかりと理解したうえで、適切な行動ができるように、持ち場ごとに具体的な業務フローを記載しておくと親切です。
細かすぎる内容まで書く必要はありませんが、いつまでに持ち場につき、どの時間帯に何をすればいいのかがわかるよう、時系列に沿って記載するとよいでしょう。
特に、直接参加者と接する持ち場を担当するスタッフ向けには、想定される質問や解答例など、トークスクリプトを用意しておくと、迷わずスムーズな対応が可能になります。
8.配布物のリスト
資料やノベルティの管理については、イベントの細かな準備の中でも特に注意が必要です。
当日配布物が足りずに参加者への配布ができない事態になると、参加者の満足度が下がるリスクがあります。
そのため、配布物のリストを作成し、資料はノベルティなどの種類、数量、配布するタイミング、保管場所を具体的に一覧化しましょう。
急な参加者の増加や配布時の不備などに備えて、予定より多めに予備も用意しておくと安心です。
9.備品リスト
備品の準備不足は、イベント当日の大きな混乱につながります。
必要な備品をカテゴリーごとに整理し、数量や調達方法まで細かくリストアップしておきましょう。
例えば、受付用品なら「参加者リスト」「名札」「筆記用具」、会場設営なら机椅子の数の他、「案内板」「養生テープ」「延長コード」など、エリア別に何がどれだけ必要なのかを明確にしておきましょう。
リスト化する際には設置場所の記載の他に、会社から持ってくるのか、会場の備品をレンタルするのかなどの調達方法を明確にしておくと、抜けもれがなくなります。
なお、レンタル備品などは原状復帰で不足なく返却できるよう、記録可能な状態にしておくと安心です。
10.スタッフの注意事項
イベントに対する印象は、スタッフの対応で大きく変わります。
参加者に気持ちよく過ごしてもらうため、スタッフ全員で服装や対応についてのポイントを共有しておきましょう。
具体的には、服装や態度、言葉遣いなど、ビジネスマナーを基本とする守るべきルールを明確にしておくのが大切です。
特に、「参加者目線での対応」「緊急時の冷静な判断」「チーム内での協力体制」といった点を重視し、主催者としての品格を保つための具体的な指針を示します。
全てのスタッフが統一された基準で行動すれば、参加者からの信頼性を高められるでしょう。
11.緊急時対応
緊急時対応計画の策定は、参加者の安全確保において最も重要な要素です。
あらかじめ必要な情報をマニュアルに落としこみ、スタッフ全員で情報共有しておくことで、災害や事故などの緊急事態が
発生した際に、迅速かつ適切な対応を取り、被害を最小限に抑えられます。
具体的には、想定される緊急事態ごとの対応手順、連絡先リスト、避難経路図を明確に記載します。
また、救護室や救急用品の場所、近隣の病院連絡先なども、すぐに確認できるようリスト化しておきましょう。
参加者の体調不良や怪我への対応手順も「救護担当者に連絡→救護室への誘導→必要に応じて救急車の要請」など、具体的な手順を時系列で示します。
緊急連絡先リストには、警察や消防、近隣医療機関の番号に加え、会場管理者や主催者側の担当者連絡先も含めておくと安心です。
参加者の安全確保を最優先事項として位置づけ、その後の対応の手順まで含めて明確化するのが大切です。
イベントの段取りを整えて当日を落ち着いて迎えましょう!

入念に準備すれば、イベント当日を自信を持って迎えられます。
運営マニュアルをしっかりと作り込み、必要なものを抜けもれなく手配していけば、大きな失敗を防げるようになります。
より成功に近づけるためには、会場スタッフとの打ち合わせを重ね、施設の特徴や注意点を細かく確認しておくのが大切です。
会場選びの段階から担当者に相談することで、過去の実績に基づいたアドバイスを得られます。
例えば、人数に応じた最適な会場レイアウトや、参加者の動線計画など、経験に基づく具体的な提案を活用できます。
また、本記事で紹介した備品リストや進行表、スタッフ配置図などの資料は、できるだけ早めに準備を始めることをお勧めします。
一つひとつ丁寧に確認していけば、当日のスムーズな運営につながるはずです。
会場選びに失敗したくない方は、イベント会場レンタルで失敗しない選び方|会場運営者視点の下見のポイントも紹介の記事もご確認ください。

「自分にぴったりの会場がどれかわからない…」
”会場のプロ”がおすすめする会場を見てみませんか?
まずは無料で会場を見てみる
Author Profile
会場探しコーディネーターメディア編集部
運営会社:株式会社シアターワークショップ
“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。
最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。
本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。
▼お問い合わせフォーム▼
会場探しのご相談はコチラ
Pick Up
関連記事
イベント運営は、多くの人の協力と細かい準備が必要ですが、それでも予期せぬトラブルが発生することがあります。 「何から手をつければいいのか分からない…」「緊急時にパニックになりたくない」と不安を感じる方...