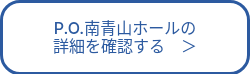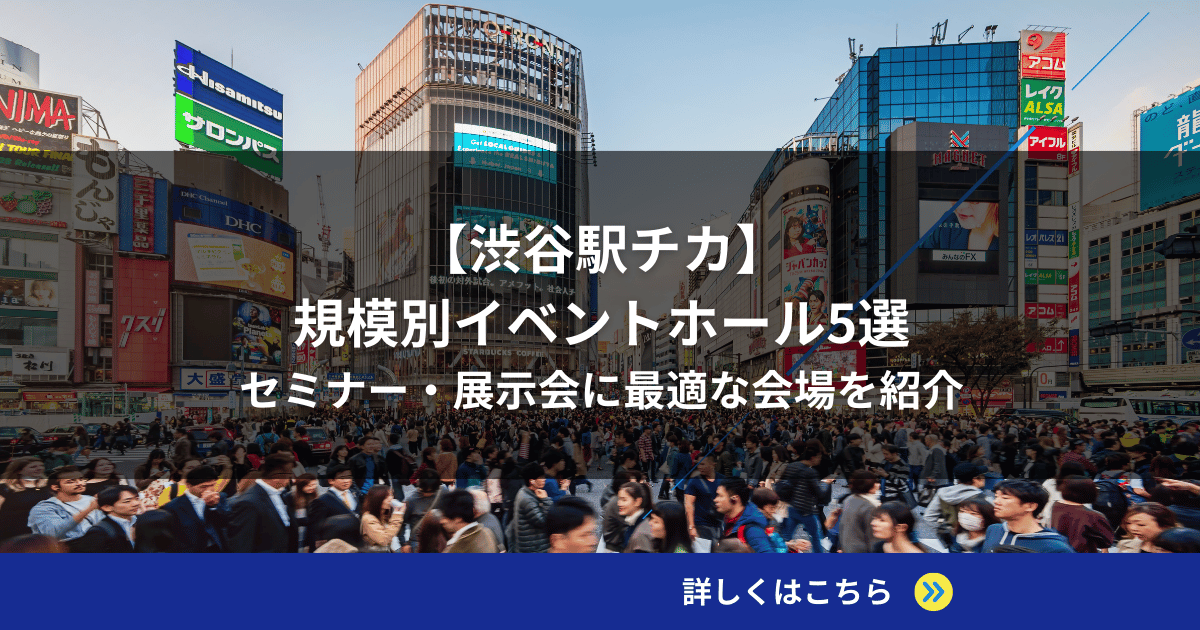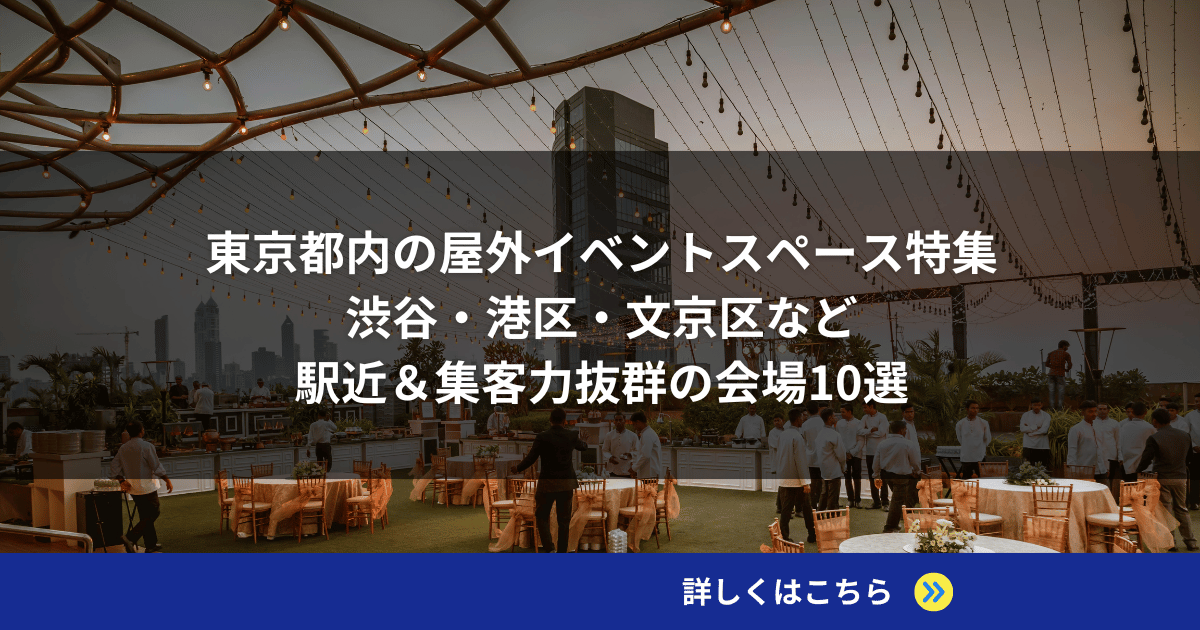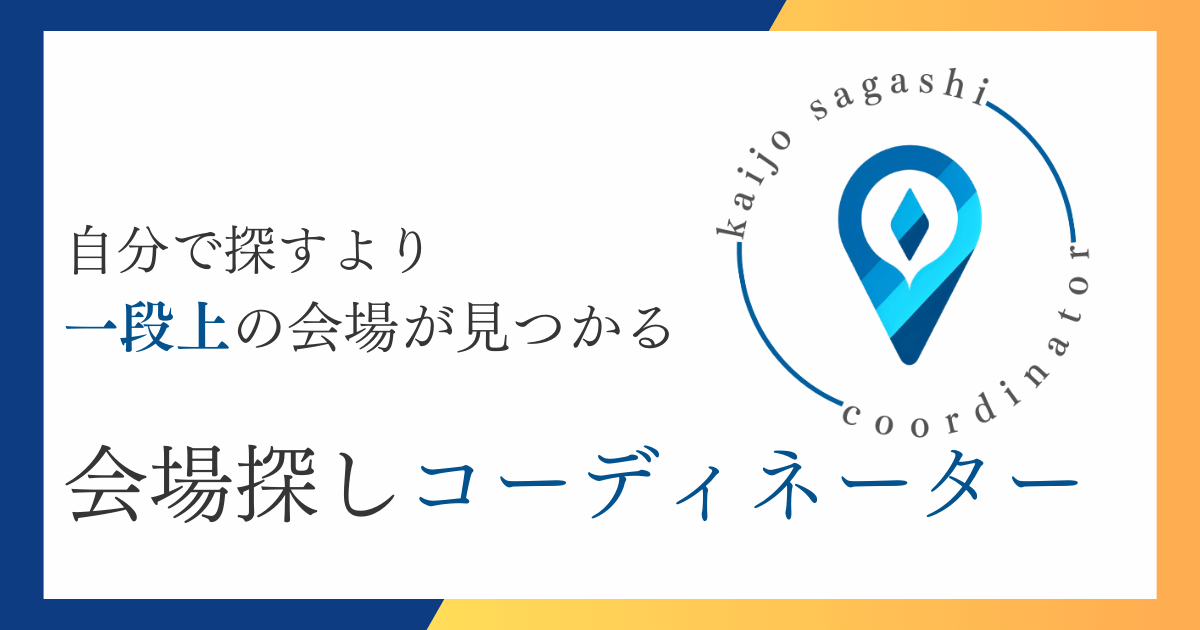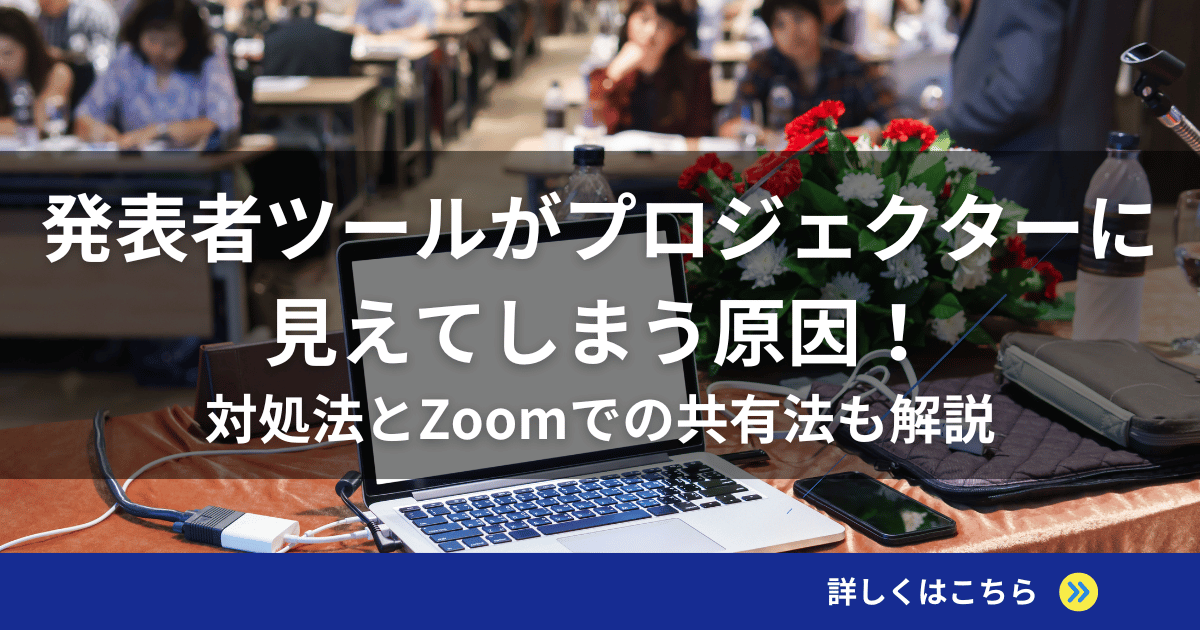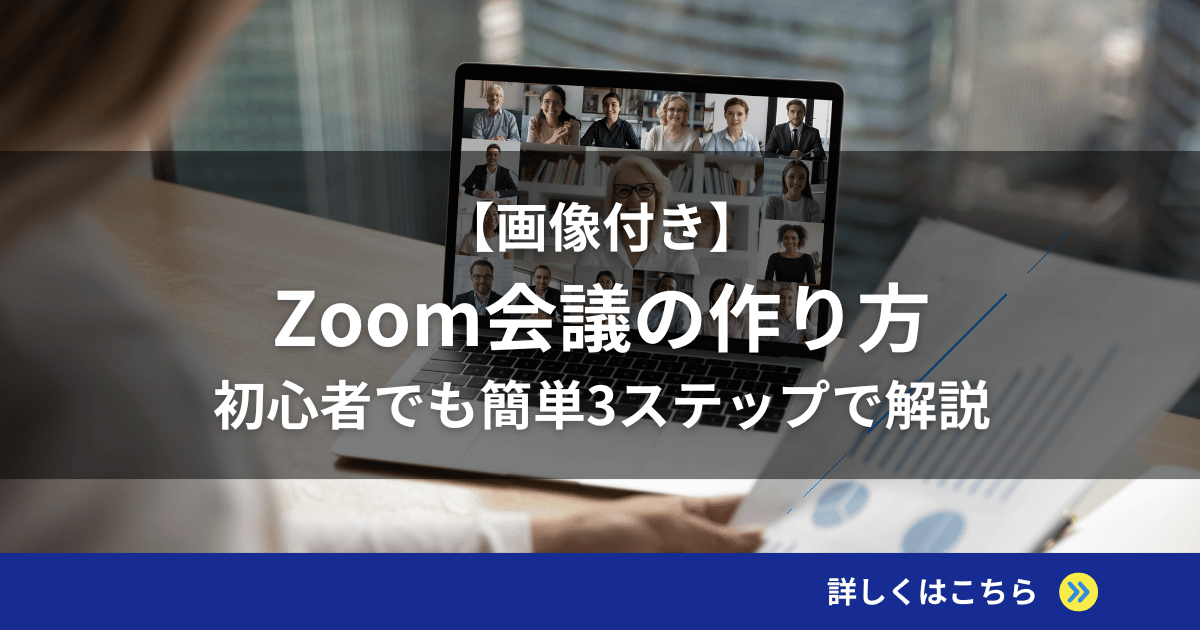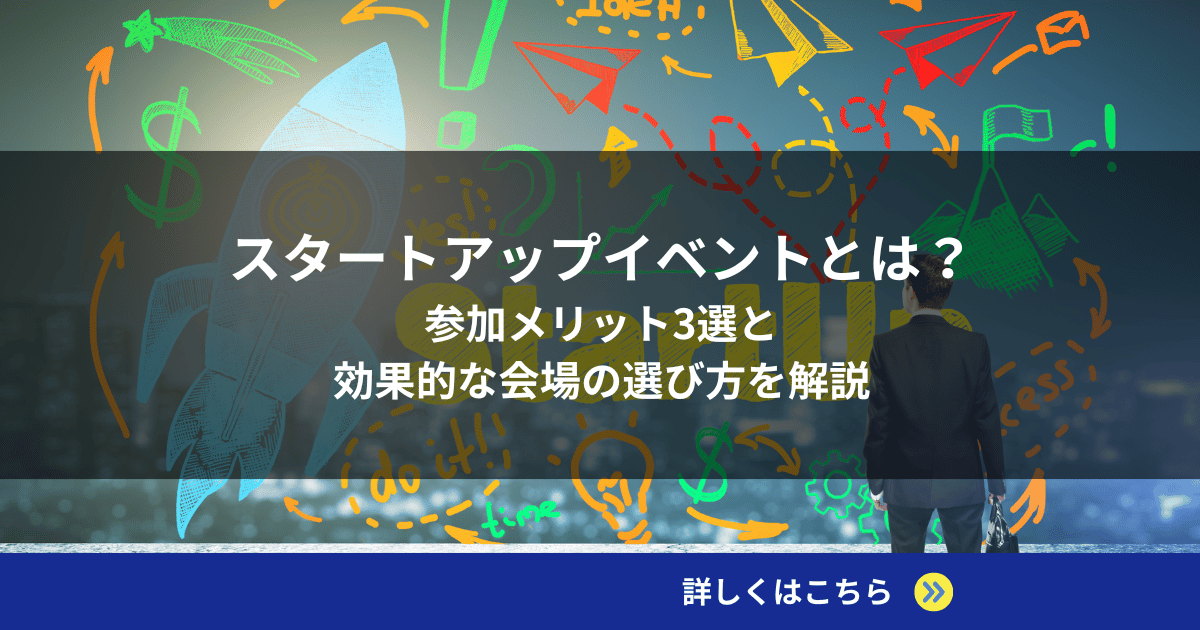サステナブルイベントとは?企業価値向上につながる持続可能なイベントについて解説
「サステナブルなイベントって何から始めればいいの?」
「環境に配慮したイベントは本当に効果があるの?」
そう思う方もいるかもしれません。
サステナブルイベントは環境負荷を減らすだけでなく、企業イメージの向上やコスト削減、新たなビジネス機会の創出にもつながる重要な取り組みです。
特に近年、持続可能性への関心が高まる中で、サステナブルなイベント開催は企業の競争優位性を築く重要な要素となっています。
この記事では、サステナブルイベントの基本概念から具体的な実践方法、具体的な事例まで、イベント企画初心者の方にも分かりやすく解説します。
環境に配慮しながらも効果的なイベントを開催するためのノウハウを、ぜひご活用ください。
目次
サステナブルイベントとは?その重要性と背景
持続可能性への取り組みが企業活動の重要な要素となる中、イベント業界でも「サステナブルイベント」という概念が注目を集めています。
ここでは、サステナブルイベントの基本的な考え方と、その背景にあるSDGsとの関連性について解説します。
サステナブル(持続可能性)の基本的な考え方
サステナブルとは、「持続可能な」という意味で、地球環境を保護しながら限りある資源を効率的に利用し、現在と未来の世代が豊かに暮らせる社会を目指すという概念です。
イベントにおけるサステナブルな取り組みとは、イベントの企画・運営・撤去の全過程において、環境への負荷を最小限に抑えながら、参加者にとって価値のある体験を提供することを意味します。
具体的には、CO2排出量の削減、廃棄物の最小化、資源の有効活用、地域経済への貢献などが含まれます。
従来のイベント運営では、短期間での大量消費や使い捨て文化が当たり前とされてきましたが、サステナブルイベントでは「長期的な視点での価値創造」を重視します。
これにより、イベント自体の質を向上させながら、社会全体への貢献も実現できるのです。
SDGs(持続可能な開発目標)との関連性
国連が2015年に採択したSDGs(Sustainable Development Goals)は、17の目標と169のターゲットから構成される国際的な開発目標です。
これらの目標は、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すためのロードマップとして位置づけられています。
サステナブルイベントは、SDGsの多くの目標と深く関連しています。
例えば、目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」では再生可能エネルギーの利用、目標12「つくる責任つかう責任」では持続可能な消費・生産パターンの確保、目標13「気候変動に具体的な対策を」ではCO2削減といった具体的な取り組みが求められます。
企業がサステナブルイベントを開催することで、これらのSDGs目標達成に貢献し、国際社会からの信頼獲得やステークホルダーからの評価向上につなげることができます。
また、SDGsへの取り組み姿勢は、特に若い世代の従業員や顧客からの共感を得やすく、人材確保や顧客ロイヤリティの向上にも寄与します。
サステナブルイベントがもたらすメリット
サステナブルイベントを開催することで、企業は様々なメリットを享受できる一方、イベント特有の環境負荷という課題にも向き合う必要があります。
ここでは、その両面について詳しく解説します。
企業イメージ向上とブランド価値の強化
サステナブルイベントの開催は、企業の社会的責任(CSR)への取り組み姿勢を明確に示す効果的な方法です。
環境への配慮や社会貢献を重視する現代において、こうした取り組みは企業ブランドの価値を大幅に向上させます。
特に、ミレニアル世代やZ世代といった若い消費者層は、企業の社会的責任への取り組みを重視する傾向が強く、サステナブルな企業に対しては指示を表明してもらいやすいです。
また、このようなイベントは対外向けだけでなく、従業員のモチベーション向上にも大きく寄与します。
自分が働く会社が社会に貢献していることを実感できるイベントは、従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の定着や新たな人材の獲得にも効果を発揮します。
これらの効果は、長期的な企業価値の向上として現れ、投資家からの評価も高めることにつながります。
コスト削減と新たなビジネス機会の創出
サステナブルイベントは、一見コストがかかるように思われがちですが、実際には多くの場面でコスト削減効果を生み出します。
ペーパーレス化による印刷費の削減、リユース資材の活用による設営費の削減、食品ロス対策による飲食費の最適化など、様々な分野でコストダウンが可能です。
特に、デジタルツールを活用したペーパーレス化は、印刷・配送・在庫管理のコストを大幅に削減できます。
QRコードを活用した資料配布やアプリを使った参加者との双方向コミュニケーションは、コスト削減と同時に参加者の利便性向上も実現します。
さらに、サステナブルイベントは新たなビジネス機会の創出にもつながります。
環境配慮型のサービスを提供する企業とのパートナーシップ、サステナビリティに関心の高い新規顧客層の獲得、異業種との連携による革新的なソリューションの開発など、従来のイベントでは得られなかった機会を生み出します。
これらの機会は、長期的なビジネス成長の基盤となる重要な資産です。
イベント特有の環境負荷に関する課題
一方で、イベントは本質的に多くの環境負荷を伴う活動であることも事実です。
参加者の移動による交通機関からのCO2排出、電力消費による間接的なCO2排出、使い捨て容器や装飾材による廃棄物の発生、資源の大量消費など、様々な課題があります。
特に大規模なイベントでは、短期間に集中的にエネルギーや資源を消費するため、環境への影響は決して小さくありません。
例えば、1万人規模のイベントでは、参加者の移動だけで数十トンのCO2が発生することもあります。
また、装飾や設営に使用される資材の多くが一度限りの使用で廃棄される現状も、大きな課題として残されています。
これらの課題を解決するためには、イベントの企画段階から環境負荷を意識した設計を行い、運営プロセス全体を見直す必要があります。
ちなみに、イベント施工においては、出展ブースの基礎施工を再利用可能なシステムパネルで組み上げるのが一般的になっています。
完璧を求めるのではなく、現状よりも改善する「より良い」を目指すアプローチが重要です。
小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな環境負荷軽減につながります。
サステナブルイベントを実現するための具体的なポイント6選
環境負荷を最小限に抑えながら効果的なイベントを開催するためには、具体的で実践的な取り組みが必要です。
ここでは、会場選定からエネルギー消費まで、各段階でのサステナブルな運営方法を詳しく解説します。
①環境に配慮した会場選び
サステナブルイベントの成功は、会場選びから始まります。
最も重要なポイントは、公共交通機関からのアクセスが良い会場を選択することです。
参加者の移動に伴うCO2排出量を大幅に削減でき、車でのアクセスを前提とした郊外の会場と比較して、環境負荷を30〜50%削減できる場合もあります。
会場選定の際は、こうした環境配慮型サービスの有無も重要な判断基準となります。
なお、イベント会場においてもSDGsを推進している建物も存在します。
例えば、東京の南青山に位置するP.O.南青山ホールは、再生可能エネルギーによる電力供給を採用するといった建物全体としての取り組みがあるホールです。

出典:https://po-hall.jp/
Well-beingな機能を備える
オフィスビル内のイベントホール
POLA青山ビルディングはビル全体として心身の健康性や快適性を維持できる Well-being な機能を備えながら、アートや文化体験に触れる事の出来る心を豊かにする空間を目指しています。SDGsとも密接に関わり、再生可能エネルギーによる電力供給を採用するなど、持続可能性を実現する社会的な問題の解消に取り組んでいます。
②持続可能な設営・装飾の工夫
イベントの設営・装飾においては、リユース可能な資材を積極的に活用することが重要です。
アルミフレームとファブリック素材を組み合わせたブースシステムは、軽量で組み立てが簡単な上、繰り返し使用が可能で、長期的なコスト削減にもつながります。
また、リサイクル素材を使用した装飾品や、長期間の利用を前提としたデザインを採用することで、廃棄物の発生を最小限に抑えられます。
他にも、ダンボール什器の活用も効果的な手法です。
軽量で加工が容易なダンボールは、オリジナルデザインの什器を低コストで製作でき、使用後はリサイクルが可能です。
アウトドア用品のレンタルも、設営の多様性を確保しながら資源の有効活用を実現する優れた方法として注目されています。
イベントとの相性によってこれらの手法を組み合わせると、魅力的な空間演出と環境配慮を両立できます。
③フードロス対策とサステナブルなケータリング
飲食提供における食品ロス削減は、サステナブルイベントの重要な要素です。
規格外野菜を積極的に活用することで、通常は廃棄される農産物を有効利用でき、生産者への支援にもつながるでしょう。
規格外の野菜は品質に問題がないうえに、通常より安価で調達できるため、コスト削減効果も期待できます。
また、近年注目されている取り組みとして、未活用素材からのクラフトジン製造などがあります。
規格外の果物や余った食材を原料として、オリジナルの飲み物を製造することで、廃棄物の削減と付加価値の創出を同時に実現できます。
他にも、適量発注による食べ残し・飲み残しの削減も重要なポイントです。
過去のデータを基に参加者数と消費量を正確に予測し、必要最小限の量を発注することで、食品ロスを大幅に削減できます。
④ペーパーレス化とデジタルツールの活用
デジタル技術を活用したペーパーレス化は、最も効果的で実践しやすいサステナブルな取り組みの一つです。
パンフレットや資料の電子化により、印刷に伴う紙の使用量とCO2排出量を削減できるだけでなく、参加者にとってもスマートフォンやタブレットで手軽にアクセスできる利便性があります。
QRコードを活用した情報提供システムは、特に効果的です。
ポスターや展示物にQRコードを設置することで、詳細な資料や動画コンテンツにアクセスでき、限られた展示スペースでも豊富な情報を提供できます。
また、リアルタイムでの情報更新も可能で、最新の内容を常に提供できる点も大きなメリットです。
専用アプリの開発も検討価値が高い取り組みです。
イベントスケジュール、会場案内、参加者同士のネットワーキング機能、アンケートやフィードバック機能などを統合することで、紙ベースの運営を完全にデジタル化できます。
どうしても紙媒体が必要な場合は、環境配慮型インクやFSC認証紙などの持続可能な素材を選択することが重要です。
⑤廃棄物削減とリサイクルの徹底
廃棄物管理は、サステナブルイベントの成功を左右する重要な要素です。
イベント開始前に廃棄物の分別計画を策定し、参加者も巻き込んであらかじめ分別方法を明確に伝えることで、リサイクル率を大幅に向上させることができます。
また、リユース・リサイクル製品の導入も効果的です。
例えば、再生紙を使用した配布物、リサイクルプラスチックで作られた什器、生分解性素材を使用した容器などを積極的に採用することで、循環型の資源利用を実現できます。
他にも、生ごみの処理においては、コンポスト(堆肥化)システムの導入が注目されています。
イベント会場でのコンポスト設備の設置や、近隣の農家との連携による生ごみ回収システムの構築により、有機廃棄物を有効な資源として活用可能です。
これらの取り組みは、廃棄物削減と同時に地域循環型社会の構築にも貢献します。
⑥エネルギー消費の抑制
イベントにおけるエネルギー消費の削減は、CO2排出量削減の観点から非常に重要です。
わかりやすい例でいえば、LED照明の活用は最も基本的でありながら効果的な取り組みです。
従来の白熱電球や蛍光灯と比較して、LED照明は消費電力を50〜80%削減でき、発熱量も少ないため空調負荷の軽減にもつながります。
また、空調システムの適正管理も大きな省エネ効果をもたらします。
参加者数に応じた温度設定、時間帯別の調整、自然換気の積極的な利用などにより、空調による電力消費を20〜30%削減することが可能です。
他にも、太陽光発電システムのレンタル、グリーン電力の購入、バイオマス燃料を使用した発電機の導入などにより、再生可能エネルギーの比率を高めることができます。
これらの取り組みは、エネルギーコストの長期的な安定化にも寄与し、経済的メリットも期待できます。
【事例紹介】サステナブルイベントの先進的な取り組み
実際にサステナブルイベントを成功させた企業や団体の事例を通じて、具体的な取り組み方法とその効果について学んでいきましょう。
各事例の工夫点や成果は、今後のイベント企画の参考になるはずです。
野外音楽フェスティバルにおける環境配慮(RISING SUN ROCK FESTIVAL、ロハスフェスタ)
大規模な野外イベントにおけるサステナブルな取り組みとして、RISING SUN ROCK FESTIVALとロハスフェスタの事例が注目されています。
これらのイベントでは、数万人規模の参加者を対象とした環境配慮の取り組みが実践されており、その規模と効果の両面で優れた成果を上げています。
RISING SUN ROCK FESTIVALでは、徹底したゴミの多分別システムを導入し、参加者にも積極的な協力を呼びかけています。
プラスチック削減のための取り組みとして、マイ食器・マイボトルの持参を推奨し、会場内での使い捨て容器の使用を大幅に削減しました。
こうした取り組みは、参加者の環境意識向上にも大きく寄与し、日常生活での環境配慮行動の促進にもつながっています。
サステナブルをテーマにした専門展示会
サステナビリティ自体をテーマとした専門展示会も、サステナブルイベントの重要な事例として注目されています。
サステナブルファッションEXPO、サステナブル・ブランド国際会議、SDGs・ESG支援EXPO、SMART ENERGY WEEK、サステナブルマテリアル展などは、その分野の最新動向を紹介しながら、イベント運営自体もサステナブルな手法を実践しています。
これらの展示会では、出展ブースの設営においても環境配慮が徹底されています。
リサイクル素材を使用したブース設営、LED照明の完全採用、デジタルサイネージによる情報表示など、従来の展示会とは一線を画す取り組みが実践されています。
また、来場者に対してもデジタルカタログの配布、QRコードによる資料提供、専用アプリでの情報共有など、ペーパーレス化が徹底されています。
特に注目すべきは、これらの展示会が単なる環境配慮の実践にとどまらず、新たなビジネス機会の創出にも大きく貢献していることです。
サステナブル関連の新技術や新素材の発表の場として機能し、出展企業と来場企業の間で多くの新規取引が生まれています。
この成功例は、サステナブルイベントが環境配慮とビジネス成果を両立できることを明確に示しています。
まとめ

サステナブルイベントは、環境保護への貢献だけでなく、企業の競争優位性を築く重要な戦略ツールとして位置づけられています。
企業イメージの向上、コスト削減、新たなビジネス機会の創出など、多面的なメリットを享受できるサステナブルイベントは、もはや企業活動において不可欠な取り組みとなっています。
重要なのは、完璧を目指すのではなく、現状からの改善を積み重ねることです。
ペーパーレス化から始める、リユース資材を一部導入する、地元の食材を活用するなど、小さな取り組みでも確実に環境負荷の削減につながり、参加者や社会からの評価向上に寄与します。
これらの取り組みを通じて得られる経験とノウハウは、将来のより大規模なサステナブルイベントの基盤となります。
サステナブルなイベントの開催をご検討中の企業様は、まず現在のイベント運営プロセスを見直し、改善可能な点を洗い出すことから始めることをおすすめします。
サステナブルなイベントの実施会場をお探しの方は、失敗しないイベント会場の選び方の記事もご覧ください。
Author Profile
会場探しコーディネーターメディア編集部
運営会社:株式会社シアターワークショップ
“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。
最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。
本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。
▼お問い合わせフォーム▼
会場探しのご相談はコチラ
Pick Up
関連記事
「スタートアップイベントって何?参加する意味はあるの?」 「どのイベントに参加すれば資金調達やパートナー探しに効果的なの?」 と悩んでいる起業家や新規事業担当者の方も多いのではないでしょうか。
「ミートアップって何?どうやって開催するの?」 「社内でイベントを企画したいけど、どんな形式がいいのかわからない」 と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。