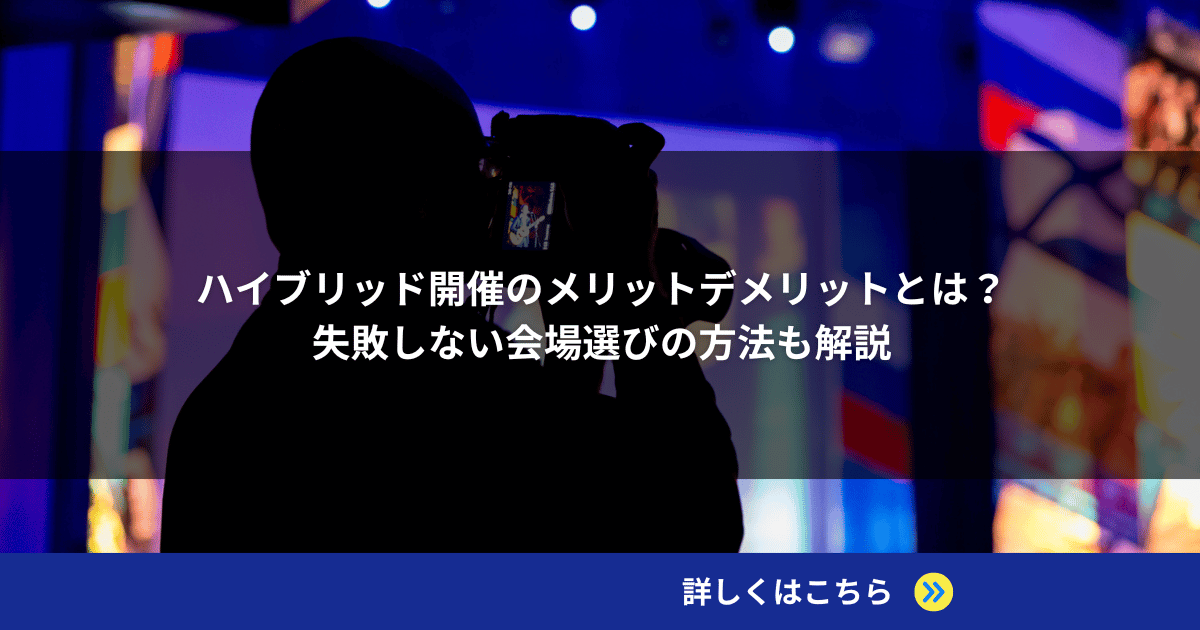シンポジウムとは?フォーラムとの違いと会場の選び方も解説
「シンポジウムの企画を任されたけれど、どう進めればいいのか分からない...」
「フォーラムとの違いって何だろう?」
そんな声をよく耳にします。
初めてシンポジウムを任された方にとって、準備から当日の運営まで、不安要素は尽きないものです。
本記事では、シンポジウムの基礎知識から実践的な運営方法、最適な会場選びまで、充実したイベントを実現するためのポイントを分かりやすく解説していきます。
都内でシンポジウムができるイベント会場をお探しの方は、渋谷駅チカイベントホール5選の記事もご参照ください。
目次
シンポジウムとは?
シンポジウムは「公開討論会」や「研究成果発表会」として知られています。
その始まりは古代ギリシア語の「一緒に酒を飲む」という意味からきた「シュンポシオン(Symposion)」です。
基本的には、特定のテーマについて複数の専門家が異なる視点から意見を述べ合う形式で行われるのが一般的です。
流れとしては、最初に各専門家がテーマに関する考えを発表する基調講演から始まり、その後は専門家同士のパネルディスカッション形式での議論と参加者からの質疑応答を通じて理解を深めます。
シンポジウムの主な特徴は、以下の3点です。
|
現代では、企業や自治体、研究団体等が主催する公開討論のイベントとしても使われており、様々な角度からテーマを深く考える機会として定着しています。
フォーラムやカンファレンスとの違いを比較
ビジネス系イベントの現場では、「シンポジウム」「フォーラム」「カンファレンス」といった用語が頻繁に使われています。
一見似ているように感じるこれらの会議形式ですが、その目的や特徴は大きく異なります。
それぞれの違いを理解することで、目的に合った最適な形式を選択できるでしょう。
フォーラム
フォーラムは、古代ローマの広場「フォルム(forum)」に由来する言葉です。
その名の通り、より開かれた公開討論の場としての性格が強いのが特徴となります。
フォーラムは、基本的には特定のテーマについて結論を導き出すことを目的としています。
一方で、シンポジウムは異なる視点からの意見交換や知見の共有が主な目的です。
企業系のイベントでは、具体的な結論や成果を求められる傾向にあることから、フォーラムがよく使用されます。
カンファレンス
カンファレンスはラテン語に由来する言葉で、「一緒に持ち寄って話し合う場」といった意味合いがあります。
カンファレンスは、シンポジウムと比較してより大規模で包括的な会議形式で、多くの参加者を集めるのが一般的です。
医療現場におけるケアカンファレンスなどは、一般参加者を募らず、組織内や特定の関係者のみを集めて実施されるクローズド型のカンファレンスと呼ばれます。
一方で、ビジネスカンファレンスでは、起業家や投資家、メディア関係者、その他一般来場者など幅広い来場者を募るケースもあります。
一般的には、複数のセッションやワークショップを並行して開催する形式がとられ、参加者が自身の関心のあるテーマを選択して参加することができます。
シンポジウムが1つのテーマを深く掘り下げるのに対して、カンファレンスは幅広いテーマを網羅的に扱う傾向にあります。
基調講演やパネルディスカッション、分科会、展示会など、様々な形式のプログラムが用意されている中で、シンポジウムをカンファレンスの1つのセッションとして組み込むケースもあるでしょう。
セミナー
セミナーは、ドイツ語の「ゼミナール(seminar)」が語源で、もともとは大学で教授と少人数の学生が特定のテーマを研究・討論する形式でした。
この形式を参考に、より広い場で意見を交わす機会として広がっていったのが現代のセミナーです。
セミナーは、一つのテーマについて専門家が講習を行う学びの場の意味合いが強く、参加者が積極的に学習に取り組むことを重視し、比較的少人数で行われます。
また、講師と参加者が直接意見を交わす時間も設けられるケースも多いです。
参加者の学習や知識習得が主な目的となり、参加者は聴講者として参加することになります。
ワークショップ
ワークショップは、英語の「作業場・工房(workshop)」を意味する言葉です。
演劇の分野で使われ始め、その後、企業研修や教育の場にも広がりました。
グループワークを取り入れるなど、参加者同士が能動的に意見交換をする形式であるのが特徴です。
グループに分かれて意見を出し合い、実際に手を動かしながら考えを深めていきます。
最後は進行役が皆の意見をまとめて結論を導き出し、グループごとに発表し、共有する形式がとられます。
シンポジウムが専門家の意見を聞き、理解を深める場であるのに対し、ワークショップは参加者が主体となって体験的に学ぶ場である点が大きな違いです。
オンラインシンポジウムの特徴
オンラインシンポジウムは、デジタル技術を活用した新しい形式として広く使われています。
完全オンラインで行うものと、会場とオンラインを組み合わせたハイブリッド型があります。
オンライン化の最大のメリットは、場所を問わず参加できることです。
海外からの参加も容易で、録画配信により、時間の制約も少なくなりました。
また、会場費や移動時間の削減など、運営面でもメリットがあります。
ただし、いくつかの課題もあります。
例えば、安定した通信環境の確保や、参加者の機器の設定など、技術面での準備が欠かせません。
また、画面越しでは参加者の集中力が続きにくく、離脱しやすいデメリットもあり、一体感も生まれにくい傾向があります。
解決手段として、チャット機能を使った双方向のやり取りや、参加型のプログラムを組み込むことで、臨場感のある会を実現できます。
また、技術的なトラブルに備えて、バックアップを用意しておくことも大切です。
シンポジウム開催までの5ステップ
シンポジウムの開催までには、相応の準備期間が必要です。
主な準備は以下のように進めていきます。
①開催方針の策定
シンポジウム開催の第一歩として実行委員会を立ち上げ、基本方針を定めます。
まず、取り上げるテーマと開催趣旨を明確にし、参加人数と予算配分を検討します。
同時に、開催月日と実施期間を決め、全体の構成内容を練りましょう。
1年前ほどから動き出すのが理想的ですが、9~6か月前からスタートするケースもあります。
②会場選定・登壇者アサイン
開催方針が決まったら、具体的な準備作業に取り掛かります。
会場を選び、現地視察や管理担当者との打ち合わせが必要です。
同時に、来賓や講師への打診と正式な依頼を進めていきます。
会場のレイアウトを作成し、必要な設備・機材も併せて検討していきましょう。
③マニュアル作成・各種手配
6か月前ごろから、開催に向けた詳細の調整を始める段階となります。
当日の実施要領をまとめ、参加者の募集も開始します。
同時に、広報・PR活動などもスタートする時期です。
運営担当者の配置も決めていき、運営マニュアルを作り始めます。
レンタル・購入備品など、イベントに必要なものをリストアップし、各所手配を進めましょう。
④直前の最終調整
1ヶ月前には会場担当者との最終打ち合わせを行い、レイアウトや使用備品等を確定していきます。
2週間前ごろには、各種発注物等の締め切りとなるケースが多いため、最終調整が必要な場合は早めに対応が必要です。
運営マニュアルや進行表など、全体の進行の流れなどを関係者とすり合わせていき、必要に応じて修正をしましょう。
また、当日は設備やシステムの動作確認を行い、リハーサルも行えると安心です。
⑤開催後のフォローアップ
シンポジウム終了後は、参加者へお礼状の送付など、フォローアップを行います。
アンケートの取りまとめを行い、最後に開催報告書を作成します。
次回以降の開催に向け、振り返りを実施するのも大切です。
シンポジウムを円滑に進めるには、多くの関係者との連携が欠かせません。
段階ごとの作業を着実に進め、関係者が密に連絡を取り合うことが大切です。
シンポジウムの会場を選ぶ際の4つの視点
シンポジウムの開催において、会場選びは想像以上に重要です。
いくら内容が充実していても、会場の設備や空間が適切でなければ、参加者の満足度は大きく下がってしまいます。
ここでは、会場選びの具体的なポイントをご紹介します。
①アクセスは良好か
会場は駅から近く、初めての参加者でも迷わずにたどり着ける場所を選びましょう。
遠方からの参加者のために、近くに宿泊施設があることも大切な条件となります。
渋谷エリアで会場をお探しの場合は、当社の運営しているヒカリエホールやスクランブルホールが渋谷駅直結となっています。
雨天時でも、外に出ることなく来場できるため、参加者の方にとって利便性の高い会場です。
②会場設備は整っているか
シンポジウムでは、映像で資料を投影しながら進行するのが基本となるため、会場内のどの席からでも見やすい位置に大型スクリーンが設置されていることが重要です。
また、配信を同時に行う場合は、安定したインターネット環境と十分な通信容量を確保し、音響設備やマイクシステムが整っていることを確認しましょう。
海外からの参加者がある場合は、同時通訳システムに対応できるか、もしくは機材の持ち込みが可能かどうかも確認が必要となります。
③快適に過ごせる環境か
シンポジウムを実施する際は、外部からの騒音が少ない環境が理想的です。
また、参加者が休憩時間を快適に過ごせるよう、自動販売機や休憩スペースの有無も確認しましょう。
長時間の開催となる場合は、会場の近くに飲食店や、コンビニエンスストアがあると便利です。
必要に応じて、ケータリングサービスの手配なども検討しておくと安心です。
④当日の準備や進行がスムーズにできるか
会場を予約する際は、当日の機材の搬入出やレイアウトの設営に必要な時間を考慮して、会場のレンタル時間を設定します。
搬入動線がスムーズかどうか、会場側での設営対応可否によっても、必要な時間が変わってくるでしょう。
また、分科会を実施する場合は、同一施設内に複数の会場があり、控室やブレイクアウトルームが確保できることが望ましいでしょう。
当社の運営している渋谷キャストスペースや、P.O.南青山ホールでは、スライディングウォールで部屋を間仕切りできるため、分科会などで隣り合わせで空間が必要な場合におすすめの会場です。
渋谷エリアで会場をお探しの場合は、「【規模別】渋谷周辺の駅チカイベントホール5選|100〜1000名対応の施設を紹介」もご覧ください。
会場探しコーディネーターがシンポジウム成功のサポートをいたします
シンポジウムを成功に導くには、十分な準備期間と適切な会場の確保が欠かせません。
運営は開催1年前の基本方針作りから始まり、会場の選定、マニュアルの作成、当日の進行まで、一つ一つ丁寧に進めていく必要があります。
なかでも会場選びは、参加者の満足度に直結する大切な要素です。
交通の便が良く、設備が整っているか、快適に過ごせる環境かなど、参加者目線での選定がポイントとなります。
さらに、機材の搬入のしやすさや、分科会用の会場確保など、運営面での使い勝手も考慮に入れましょう。
会場をお探しの方は、当社の「会場探しコーディネーター」がお手伝いいたします。
会場探すのがそもそも大変…
全部誰かに丸投げしたい…
そのようなお悩みがある方は「会場探しコーディネーター」へぜひ丸投げしてください。
ご予算や規模、ご要望に応じて最適な会場をご提案させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
都内でシンポジウムができるイベント会場をお探しの方は、渋谷駅チカイベントホール5選の記事もご参照ください。
Author Profile
会場探しコーディネーターメディア編集部
運営会社:株式会社シアターワークショップ
“劇場・ホールに関することはなんでもやっている”、トータル・シアタープロデュースカンパニー。40年にわたり構想・計画づくり、設計・施工にも携わる劇場づくりのノウハウをもとに、劇場・ホール・イベントスペース運営の専門家集団として、全国20以上の施設管理を支援。年間1,000件以上のイベントを会場管理者の立場からサポート。企業の新商品発表会、展示会、コンサート、セミナー、企業研修など、幅広い用途に対応する会場選定の実績を持つ。
最適な会場探しのノウハウを発信し、イベント主催者や企業担当者の課題解決をサポート している。
本メディアでは、会場運営のプロフェッショナル視点で、イベント成功につながるイベントスペース選びのポイントや最新トレンドを発信。
▼お問い合わせフォーム▼
会場探しのご相談はコチラ
Pick Up
関連記事
「ミートアップって何?どうやって開催するの?」 「社内でイベントを企画したいけど、どんな形式がいいのかわからない」 と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
コロナ禍以降、生活様式の変容とともに、イベント開催形式の大きな変化を実感した人も多いのではないでしょうか。

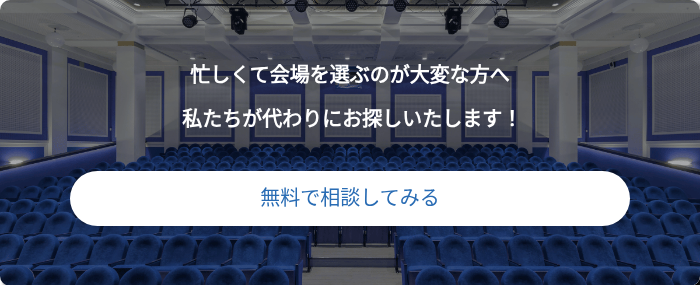

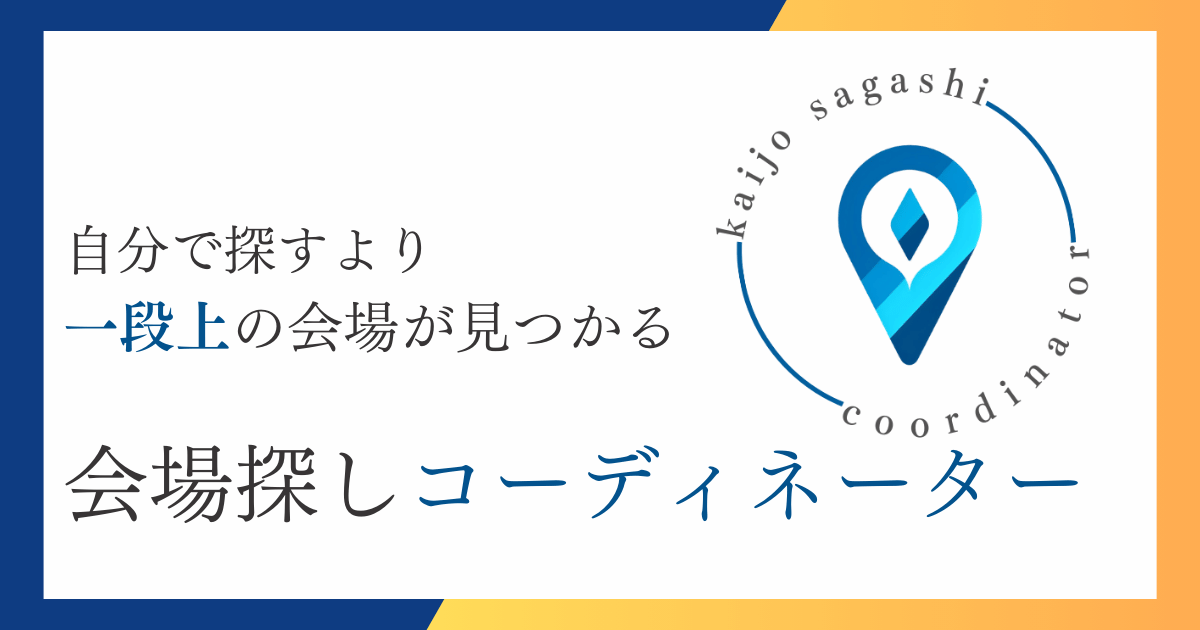
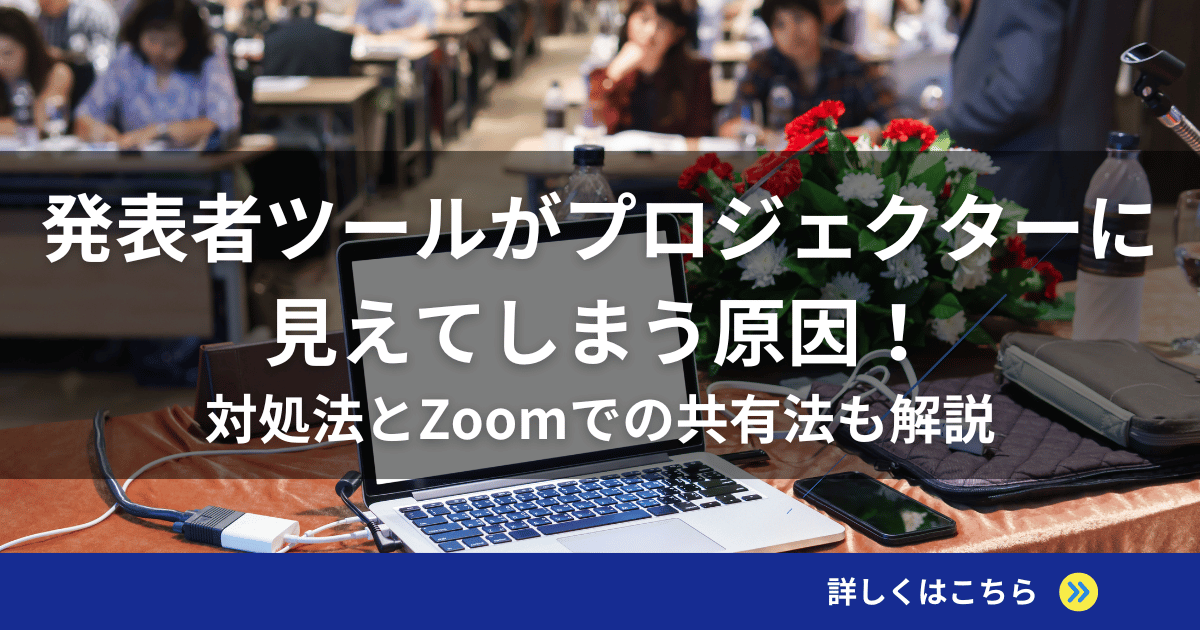

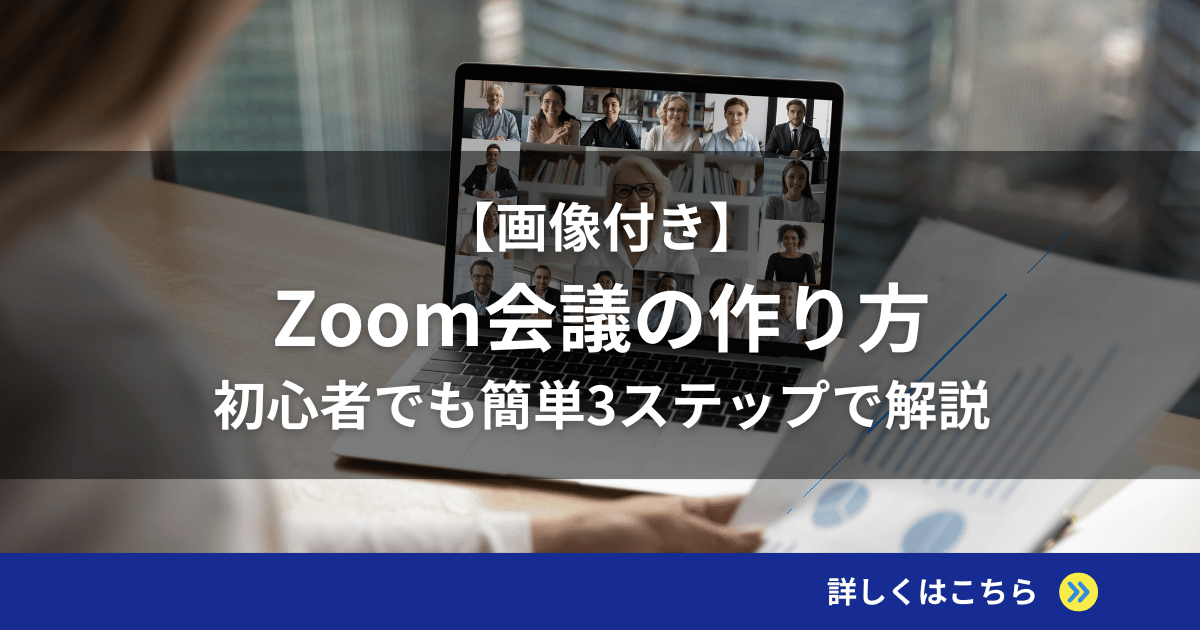

.png)